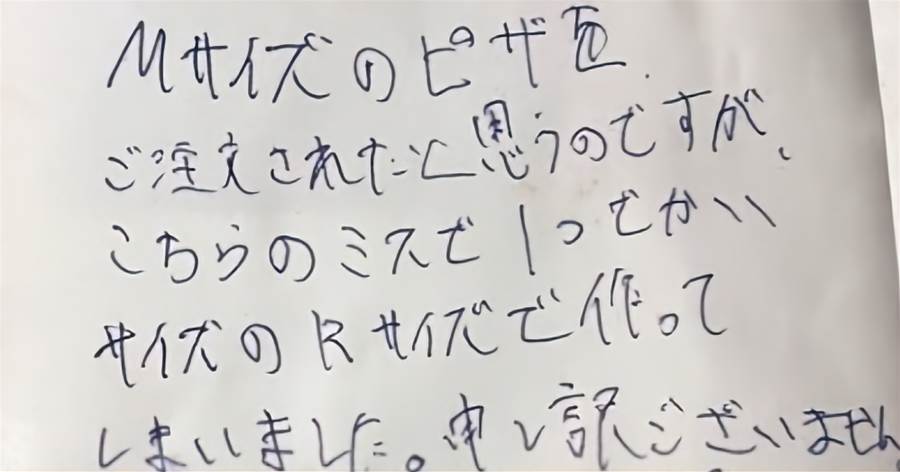年金の振込日を、私はカレンダーに小さく丸をつけて覚えていました。六万五千円。多いとは言えません。けれど、家賃を抑え、電気をこまめに消し、買い物は特売日にまとめる。そうして静かに暮らすなら、ぎりぎり成り立つ金額でした。
私は、子どもたちに頼りたくありませんでした。長男にも、次男にも、それぞれ家庭がある。私が老いたからといって、彼らの生活を乱してはいけない。
そう思って、体調が悪くても我慢し、病院も必要最低限にしていました。
ただ一つ、胸の奥で引っかかっていたのは、長男夫婦との距離でした。孫の顔を見たいと願っても、「忙しいから」と断られることが増え、連絡も次第に途切れていった。長男は昔から優しい子でしたが、結婚してからは、返事がどこかよそよそしくなった気がしていました。
そんなある日、長男から珍しく電話がかかってきました。
「母さん、今度の日曜、家に来られる?」
声は硬く、要件だけを急いで伝えるようでした。不安はありましたが、私は「分かったよ」と答え、少しだけ気持ちが明るくなりました。久しぶりに会える。孫の声も聞けるかもしれない。そう思ったのです。
日曜、私は菓子折りを小脇に抱え、約束の時間ぴったりに長男宅のインターホンを押しました。玄関を開けたのは長男嫁でした。笑顔は作っているのに、目が笑っていない。私はその時点で、胸が冷えました。
リビングに通されると、長男はソファの端に座り、視線を落としていました。孫の姿は見えません。室内は妙に静かで、時計の針の音がはっきり聞こえるほどでした。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください