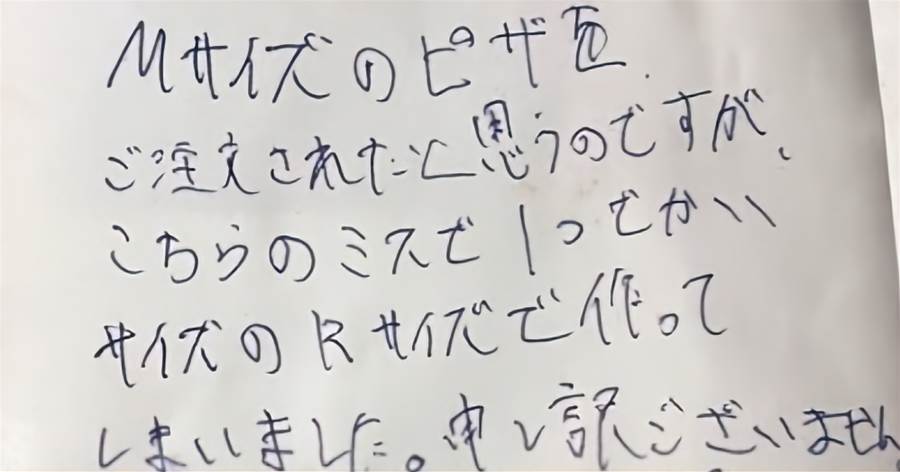満員電車の朝は、誰もが他人の存在を“障害物”として扱うほど余裕がない。肩と肩が押し合い、吊り革が軋み、車内アナウンスすら遠く聞こえる。俺もその一人だった。遅刻だけは絶対に避けたい。そう思いながら、ホームに滑り込む車両へ体をねじ込んだ。
次の瞬間だった。
「……っ、う、」
近くで小さな声がして、誰かが崩れるように倒れた。周囲が一斉に引いたせいで空間ができ、そこに“美人”と呼ばれるような女性が横たわっているのが見えた。
顔色は青白く、呼吸が浅い。瞬きが不自然に止まり、唇がかすかに震えている。
誰かが言った。
「駅員呼んで!」
「救急車!」
「触ったらヤバいんじゃ…」
その一言が、車内を一気に硬直させた。助けたいのに、関わりたくない。善意よりも怖さが勝って、全員が“責任”から逃げるために目をそらす。俺はその空気が嫌だった。
「どいてください。呼吸、確認します」
言いながら膝をつき、女性の肩を軽く叩いた。反応は薄い。脈もはっきりしない。迷っている時間が一番危ない。俺は駅員の到着を待たずに叫んだ。
「AED、ありますよね! 誰か取ってきて! 駅員にも伝えて!」
幸い、近くの乗客が走った。別の人が非常ボタンを押し、車内アナウンスが慌ただしく変わる。俺は冷静を装いながら、頭の中は必死だった。手順なんて完璧じゃない。けれど、止まった時間を動かさなきゃいけない。
AEDが届いた。ケースを開け、音声ガイドに従う。衣服をずらす手がわずかに震えたが、躊躇はしない。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください