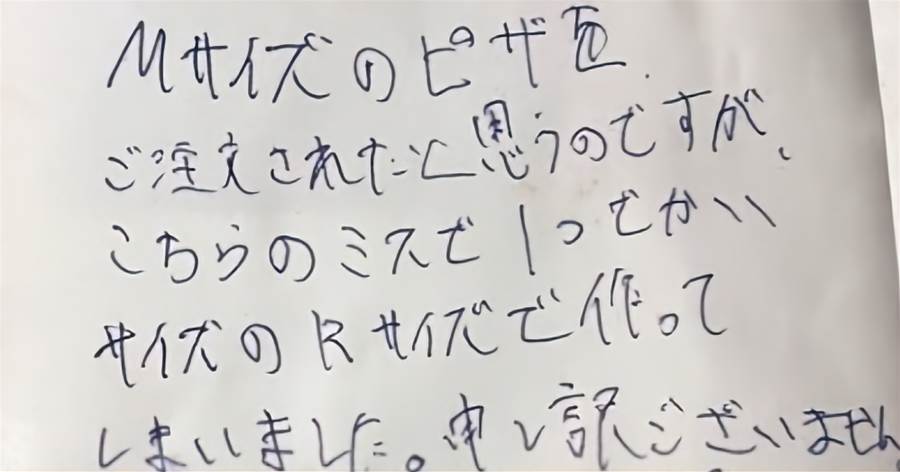手術室の灯りは、思ったよりも白く、冷たく感じました。卵巣摘出――医師の説明を何度聞いても、私はどこか他人事のように受け止めていたのです。麻酔が切れた直後、腹の奥に鈍い痛みが居座り、同時に「もう戻らないものがある」という感覚だけが、妙に鮮明でした。
病室に戻ったその日の夕方、夫は花束でも、励ましの言葉でもなく、紙の封筒を持って現れました。
顔は乾いた土のようで、目は私ではなく床を見ていました。
「……悪いけど、もう無理だ」
私は点滴の管を見つめたまま、何が起きているのか理解できませんでした。言葉が耳に届くまでに、時間がかかったのです。
「子ども、できないんだろ。俺、親に孫の顔見せたいんだよ。お前だって、女として……その……」
卵巣を失った直後の私に、夫は“女としての価値”を突きつけて去りました。見舞いの時間はまだ残っていましたが、夫はバッグを持ったまま一度も椅子に座らず、そのまま背を向けました。扉が閉まる音は小さかったのに、私の中では大きな断絶の音として響きました。
その夜、私は泣きませんでした。泣く余裕がなかったのか、涙が出るほど心が動かなかったのか、自分でも分かりません。
ただ、呼吸のたびに傷が痛み、痛みのたびに「私は今、捨てられた」という事実だけが、淡々と積み上がっていきました。
翌日、主治医の回診がありました。穏やかな口調の先生は、検査結果を手元の資料で確認しながら言いました。
「摘出した卵巣の腫瘍ですが、悪性ではありません。転移もありません。治療としては成功です」
私は胸の奥が少しだけ緩むのを感じました。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください