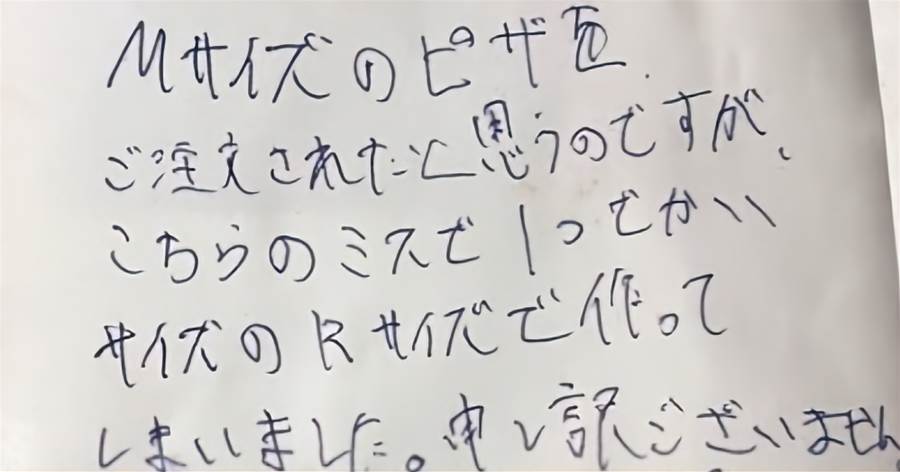弟嫁の「え?」という声は、葬儀場の静けさに不釣り合いなほど間の抜けた響きでした。香の匂い、僧侶の読経、親戚たちのすすり泣き。そのすべてが流れていく中で、彼女だけが妙に浮いて見えたのです。
私は笑いを止めたまま、涙を拭うふりをして息を整えました。悲しみの涙ではありません。こみ上げたのは、呆れと、そして確信でした。
「通帳の名義、確認した?」
私は声を荒げず、静かに繰り返しました。弟嫁は、まるで自分が何か大きな勘違いをした子どものように、視線を泳がせます。
「だって、義父の通帳に決まってるじゃん。タンスの奥にあったし、印鑑も同じところに……」
「“義父の通帳”って、どれ?」
私は問いを細くしました。彼女は勝ち誇った顔を取り戻そうとして、スマホのメモを見ながら言いました。
「これ。口座番号も控えてあるし。もう三百万、使っちゃったしね。葬儀代ってことにすればさ、みんな文句言わないでしょ? ね?」
最後の「ね?」には、同意を取りつけて逃げ道を作ろうとする卑しさが混ざっていました。
弟は隣で、青ざめたまま固まっています。父の棺の前で、なぜこんな会話が成立するのか。けれど、成立してしまうのが現実でした。
私はゆっくりと、黒いバッグから一枚のコピーを取り出しました。父が亡くなる半年前、私に預けていた書類の束。その中にあったものです。私はそれを彼女の前に置きました。
「これ、見て。名義」
弟嫁は眉をひそめ、紙に目を落としました。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください