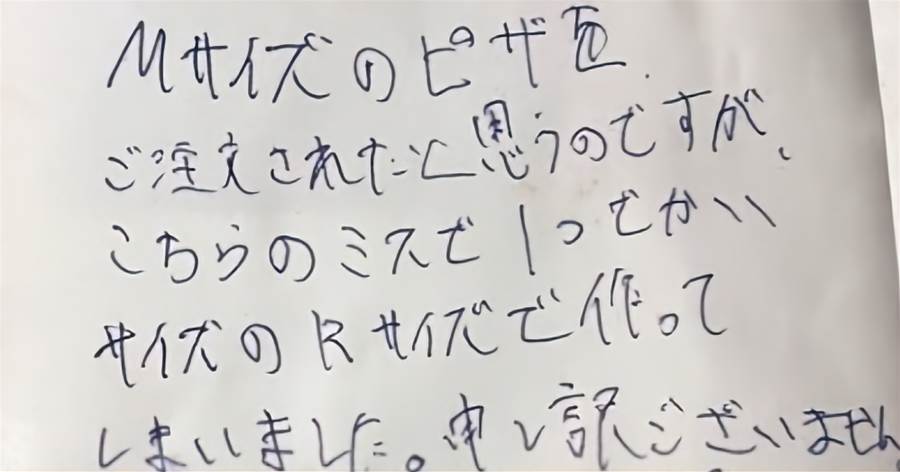家に戻るまでの道のりが、異様に長く感じた。夫はハンドルを握ったまま、ほとんど言葉を発しない。私は助手席で、警察からの電話の言葉を何度も反芻していた。
「奥様が自宅で亡くなりました。」
奥様――私だ。今ここに生きて座っている私が、家で死んでいる。そんな矛盾が、現実として成立するはずがない。けれど夫の顔は青ざめ、口元は引きつり、何かを必死に飲み込んでいるようだった。
冗談で済む反応ではない。
自宅近くに着いた瞬間、嫌でも現実が目に入った。路地の入口にパトカーが止まり、黄色い規制テープが張られている。近所の人が遠巻きに立ち、ひそひそ声が雨のように降っていた。夫は車を降りると、私の手を強く掴んだ。痛いほどの力だった。
「……待って。私、ここにいるよね?」
私がそう言うと、夫は一瞬だけ私を見た。視線が泳ぎ、次に出た言葉は、私の胸をさらに冷たくした。
「……とにかく、黙ってて。余計なこと言うな」
余計なこと。私が生きていると口にすることが、余計なのか。
玄関前には警察官が二人立っていた。私たちを見るなり、一人が無線に短く何かを告げる。すぐに別の警察官が駆け寄ってきて、夫に尋ねた。
「ご主人ですね。奥様のご親族の方は?」
夫は、答えに詰まった。私は耐えきれず、一歩前へ出た。
「奥様は私です。今ここにいます。電話は、何かの間違いでは――」
その瞬間、空気が変わった。警察官の目が大きく開き、次いで鋭く細まる。
「……失礼ですが、身分証を提示していただけますか」
私は免許証を差し出した。警察官は私の顔と免許証を何度も見比べ、低い声で同僚に言った。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください