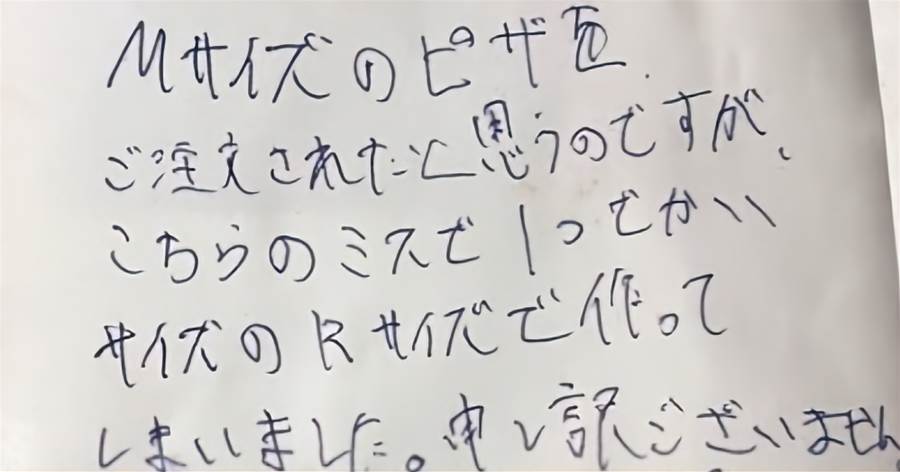救急車のサイレンが遠ざかるまで、私は玄関で立ち尽くしていた。誕生日のはずの夜が、たった数十秒で「事件」に変わってしまった。床に落ちたフォーク。崩れたケーキの一切れ。夫が倒れた場所に残る、異様な甘い匂い。何より、息子の目が怖いほど静かだった。
病院に着くと、夫は救急処置室へ運び込まれ、私は待合の椅子に座らされた。看護師が「奥様ですか」と確認し、短い説明だけを残して去っていく。
私は息子の手を握った。指先が冷たいのに、彼は震えていない。
「ねえ……どうして、あんなこと言ったの。『食べたら死ぬ』って」
息子は小さく息を吐いた。まるで大人が整理した結論を口にするみたいに、淡々と答えた。
「パパ、さっきキッチンで……白い粉を入れてた。ママに見えないように。ぼく、見ちゃった」
心臓が嫌な音を立てた。私は怒りより先に、理解できない恐怖に襲われた。誕生日ケーキに、わざわざ何かを入れる理由があるのか。家族を祝う夜に。
医師が現れたのは、その直後だった。表情は硬い。
「ご主人は現在、強い中毒症状が出ています。原因物質の特定が必要です。ご自宅で何か、異物を混ぜた可能性はありますか」
私は言葉を失い、息子を見た。息子は私より先に、医師をまっすぐ見て言った。
「ケーキ。パパが入れてた。ママの皿に」
その場の空気が変わった。医師は一瞬だけ視線を泳がせ、すぐに看護師へ指示を出した。私は、ようやく声を絞り出す。
「……私は、食べていません。息子が止めました。むしろ――夫が食べて……」
医師は短く頷き、事情聴取のような質問を重ねた。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください