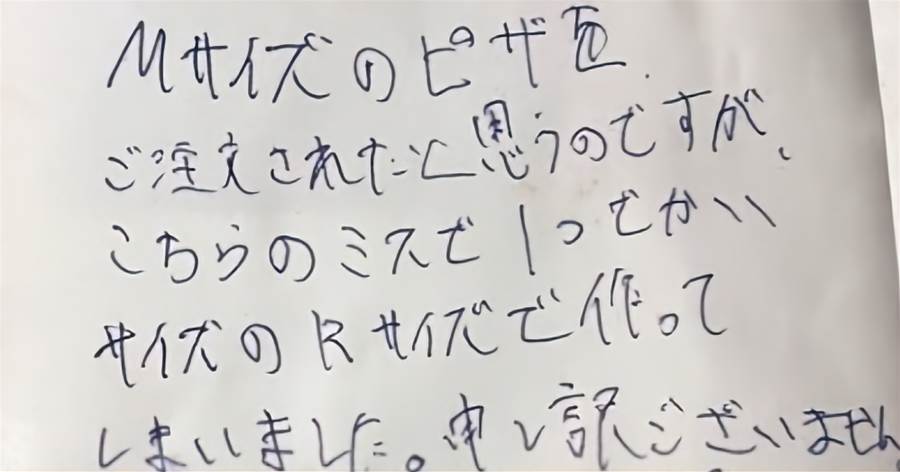大企業の本社ビルは、ガラスの壁が空を映していた。受付を抜けるだけで、こちらの“格”を測られているような気分になる。私は小さな会社の営業責任者として、資料を抱え、約束の時間ぴったりに到着した。今日の商談が決まれば、うちの資金繰りは一気に安定する。50億の融資――規模が大きすぎて現実味がないほどだが、だからこそこの一回にすべてが懸かっていた。
案内されたのは、役員フロアの会議室だった。白い壁、長いテーブル、誰も座っていない椅子。お茶だけが置かれ、扉は静かに閉まった。
……そこから、三時間。
誰も来ない。
最初の十五分は「遅れているだけ」と思えた。三十分で不安が増し、一時間を過ぎるころには、これは遅延ではなく“放置”だと確信した。秘書に問い合わせても、返ってくるのは丁寧な定型文だけ。
「担当者が立て込んでおりまして、もう少々お待ちいただけますでしょうか」
私は怒鳴らなかった。顔にも出さなかった。代わりに、資料を整え、話す順番を組み直し、質問に備えた。相手が何を試しているのかは分からないが、こちらが崩れた瞬間に負けるのは理解していた。
ただ、三時間は違う。誠意の問題だ。
時計の針が、約束の時間枠の終点に差しかかった頃、ようやく扉が開いた。入ってきたのは商談相手の役員ではなく、黒いスーツの秘書だった。彼女は一礼し、淡々と言った。
「時間です。期限切れましたので、50億の融資は白紙です」
私の中で、何かが静かに切れた。驚きよりも、納得が先に来た。これは“審査”ではない。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください