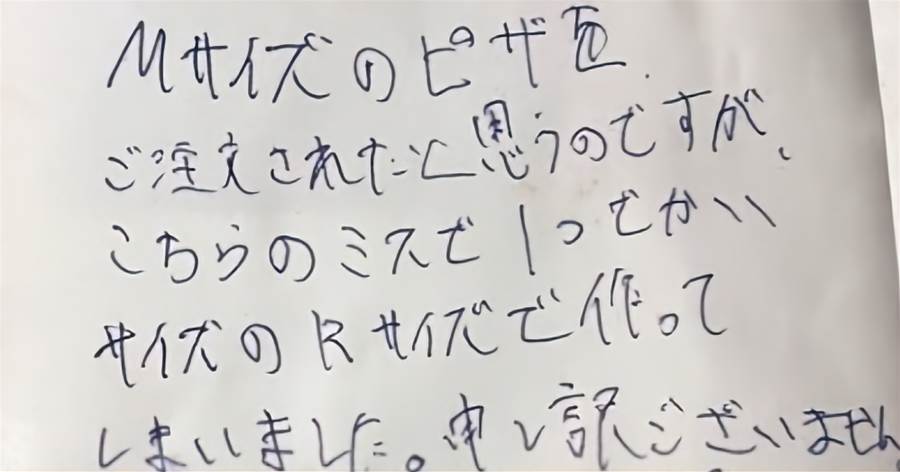雨上がりの夜だった。駅前のネオンが濡れた路面に滲み、高級寿司店「鮨 いわ瀬」の白い暖簾は、静かに客を選別するかのように揺れていた。
その店の前に、一組の老夫婦が立ち止まった。男はくたびれたコート、女は色褪せたカーディガン。どちらも新品ではない。だが、皺のつき方が丁寧で、袖口はきちんと直されている。長く大切に着てきた服だと分かる。
「ここで、間違いないかしら」
女が小さく言うと、男は頷いた。二人は予約の時間ぴったりに扉を開け、控えめな声で名乗った。
その瞬間だった。カウンター奥の若い板前見習いが、鼻で笑った。
「……え?その格好で?」
言葉は小さかったが、静かな店内では十分に響く。隣の客が視線を上げ、店の空気が一瞬だけ歪んだ。老夫婦は顔色一つ変えなかった。女は笑って、ただ頭を下げた。
「失礼いたします。予約をしておりまして」
見習いは面倒そうに帳面をめくり、わざとらしく首を傾げた。
「予約?ああ……でも、うち、ドレスコードってほどじゃないけど、最低限ってものがあるんですよね。ほら、店の格があるんで」
男は静かに言った。
「分かっております。ですが今日は、大将にご挨拶をと思いまして」
そのやり取りを、カウンターの端で聞いていた常連らしき男が笑った。
「最近、変なの増えたな。高級店を見学しに来たのか?」
店内に小さな失笑が散る。女の指が一瞬だけ震えた。しかし男は、妻の手の上にそっと自分の手を重ね、落ち着いた声を保った。
「失礼がありましたらお詫びします。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください