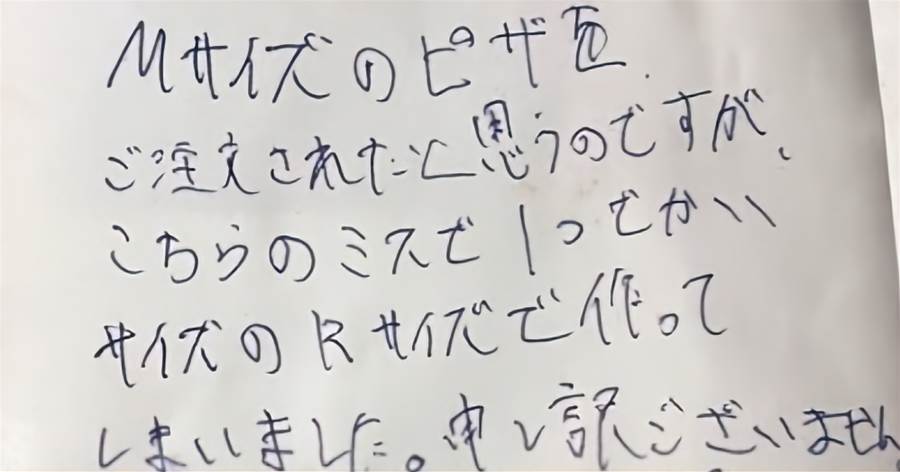兄夫婦が来たのは、雨の匂いが残る夕方でした。チャイムを押す指が震えていたのか、短く二度鳴った。ドアを開けると、そこには兄と兄嫁が立っていて、二人とも顔色が紙のように白かった。
「……お願いがある」
兄がそう言った瞬間、胸の奥がひやりとしました。昔から、兄の「お願い」はたいてい私に負担を背負わせる形で終わる。そういう記憶が、体に染みついているのです。
リビングに通す前に、二人は玄関で膝を折りました。土下座でした。床に額がつき、兄嫁の肩が小刻みに震えている。兄の声はかすれていました。
「子どもが……このままだと……助からない。移植が必要なんだ。適合するのが……お前しかいないって……」
言葉の意味が頭に入ってくるまで、少し時間がかかりました。臓器。提供。私。
その三つが結びついた瞬間、視界がすっと狭くなりました。
「子どものために、お願い。あなたの臓器を……少しでいいから……」
兄嫁が泣きながら言いました。“少しでいい”という言い方が、ひどく軽く聞こえました。臓器は、家電の部品ではない。
提供する側にも命があり、生活があり、恐怖がある。それを「少しでいい」と言える感覚が、私には信じられなかった。
私はその場で答えませんでした。玄関の冷たい空気の中、二人の頭頂部を見下ろしながら、胸の奥に溜まっていた“あの時”が、ゆっくり浮かび上がってきたからです。
「あの時されたことを、私は忘れてない」
私がそう言うと、兄は顔を上げました。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください