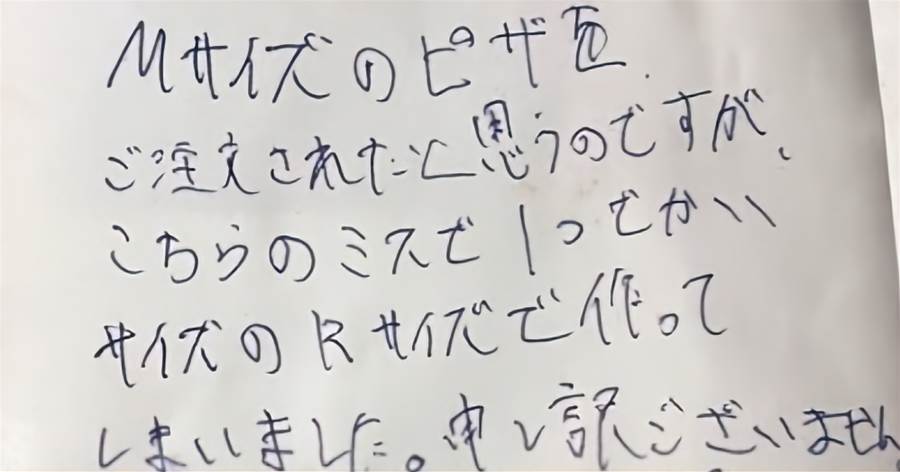夕暮れの商店街は、いつもより冷たかった。風が強く、チラシやレシートがアスファルトを滑っていく。貧乏な女子学生の私は、スーパーの閉店間際の値引き弁当を狙って、バイト帰りに急ぎ足で歩いていた。スマホの残高アプリは、見ないようにしても目に入る。今月は家賃と学費で、ほとんど余裕がない。
そのときだった。裏通りのゴミ置き場の横で、何かが崩れる音がした。
振り向くと、ゴミ箱の横に、お婆さんが倒れていた。呼吸が浅く、片手が小さく震えている。周囲には人影がない。私は一瞬だけ躊躇した。救急車を呼べばいい。そう頭では分かっていた。でも、救急車が来るまでに容体が悪化したらどうする。何より、ここは車が入りにくい細い道で、救急隊が辿り着くまで時間がかかるかもしれない。
「大丈夫ですか!」
膝をついて声をかけると、お婆さんの唇がかすかに動いた。
「……病院……お願い……」
その言葉で、迷いは消えた。私はすぐに救急に電話を入れ、位置を伝えながら、近くの総合病院が徒歩圏にあることを思い出した。距離にして十五分程度。走れば、もっと早い。
「今から運びます。
病院へ向かいます」
私は電話口の指示を聞き、できる限り安全を確保した上で、お婆さんを背負った。想像以上に軽かった。軽すぎて、逆に恐ろしくなる。骨の細さが背中越しに伝わり、私は歯を食いしばった。
夜の空気を切って走った。肩にかかる重み、鼓動、息切れ。バイト疲れの脚が悲鳴を上げる。それでも止まれない。お婆さんの体温が、少しずつ下がっていく気がしたからだ。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください