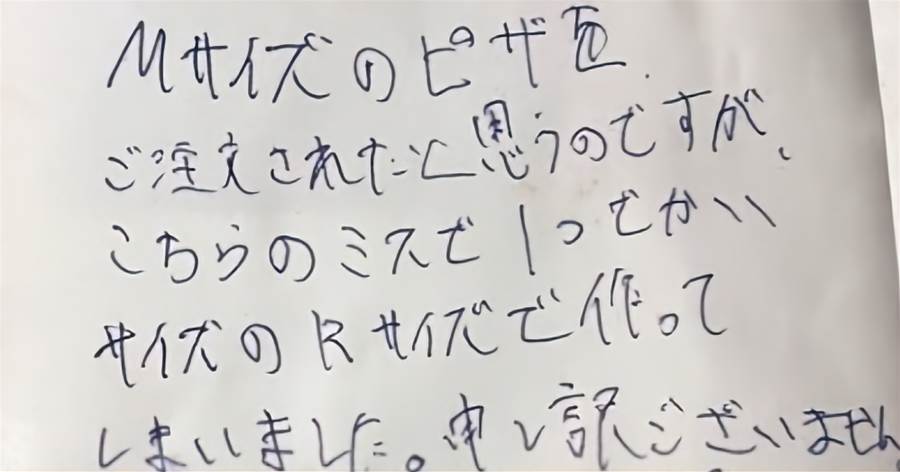弟の結婚式を翌日に控えた夜だった。私は妊娠後期で、体は重く、少し歩いただけでも息が上がる。式の準備を手伝ってほしいと弟に頼まれ、無理のない範囲で動いていたが、帰宅の電車の揺れさえ苦しく感じた。家の玄関を開けた瞬間、ようやく緊張がほどける。そう思った、その一歩目で――人生が一変した。
リビングから聞こえた足音は、急ぎ足というより怒りを引きずるような音だった。
振り向くより早く、弟の嫁、つまり明日の花嫁が目の前に現れた。視線が刺すように冷たい。私は「どうしたの?」と声をかけようとした。だが、その言葉が形になる前に、乾いた衝撃が頬を打った。
次の瞬間、視界が白く弾け、耳の奥がキンと鳴った。私はよろめき、壁に手をつこうとしたが、うまく力が入らない。頬が熱い。痛みよりも、状況が理解できない恐怖が先に来た。「なにを……」と口を開いた私に、弟嫁は息を荒くしながら、低い声で吐き捨てた。
「全部、あなたのせいで台無しになるところだった」
意味が分からない。私は反射的にお腹をかばうように両手を添えた。すると、足元に生ぬるい感覚が広がった。背筋が凍りつく。
破水だった。心臓が喉までせり上がり、呼吸が浅くなる。「救急車……」と呟いた途端、腹の奥が締め付けられ、痛みが波のように押し寄せた。
私は床に崩れ落ちた。弟嫁の顔が、遠くで歪んで見える。彼女が何か言っていたかもしれない。だが私は、ただ必死に、お腹の中の命を守りたい一心で助けを求め続けた。隣人が異変に気づき、救急の要請が入ったのはその後すぐだった。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください