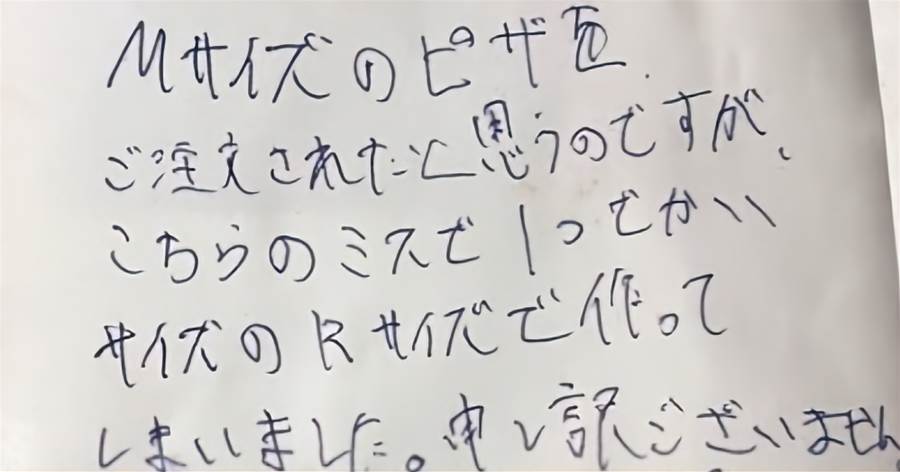急逝した義父の訃報は、平日の昼過ぎに入った。病院からの一本の電話で、私は頭の中が真っ白になり、次に来たのは現実的な段取りだった。葬儀社、親族への連絡、死亡届、寺への手配。気丈に動くしかない。
だから私は、真っ先に夫へ電話をかけた。夫は義父の実の息子だ。こういう時こそ、夫婦で支え合うべきだと思った。
──しかし、繋がった瞬間に返ってきたのは、信じがたい言葉だった。
「今、両親と温泉旅行中!親孝行中の邪魔するな!」
一瞬、言葉の意味が理解できなかった。両親? 義父は今、亡くなったばかりだ。私は状況を伝えようとしたが、夫は聞く姿勢すら見せず、苛立った声を重ねた。
「面倒事はお前がやれ。俺に連絡してくるな。とにかく邪魔するなよ」
プツリ、と通話が切れた。耳元に残ったのは、温泉宿のざわめきのような音と、夫の乱暴な息遣いだけだった。
私はしばらく受話器を握ったまま立ち尽くした。悲しみより先に、胸の奥が冷え切っていく感覚がした。義父の死を「面倒事」と言った人間が、同じ家にいる。その事実が、私の心を静かに折っていった。
そして私は、夫の言葉通りにした。
──一切、連絡しなかった。
葬儀社との打ち合わせも、親族への連絡も、火葬場の予約も、香典返しも、すべて私が一人で進めた。義母はショックで気丈さを保てず、私は彼女の手を握りながら、淡々と必要事項を確認していった。涙を流す時間は夜に回し、昼は段取りに徹した。
通夜の日、夫の席は空いたままだった。親族から「ご主人は?」と聞かれるたび、私は言葉を選んだ。真実を言えば場が荒れる。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください