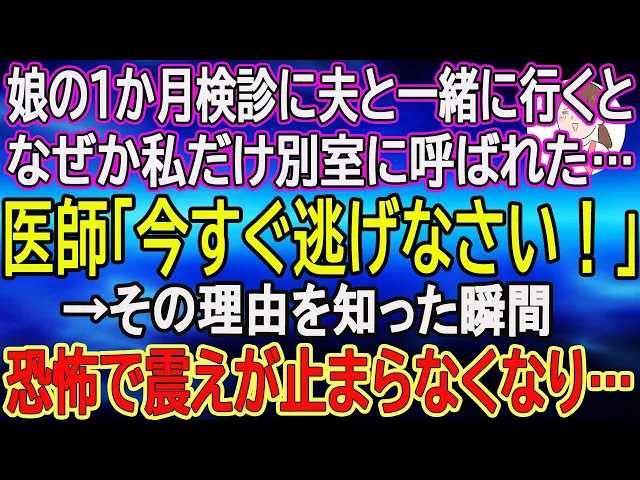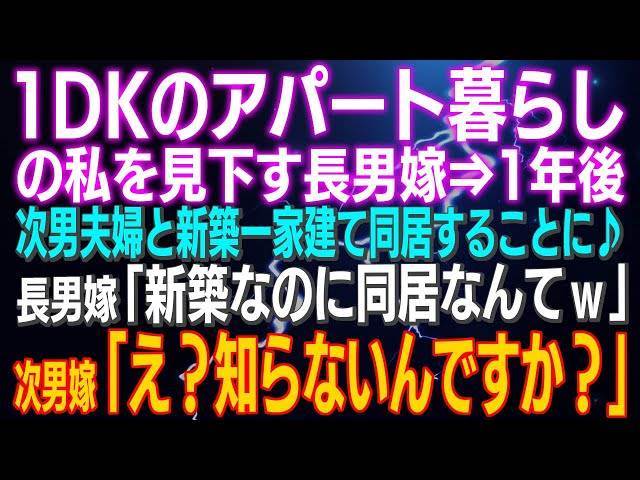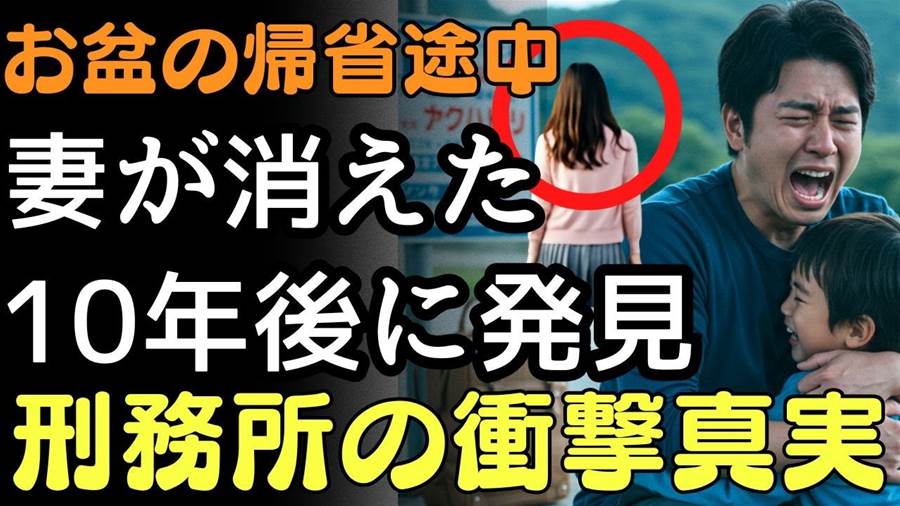
一九九八年八月十五日。
お盆の東名高速は、帰省客の熱と焦りで煮立っていた。武田サービスエリアに入るだけで三十分――太郎の握るハンドルは汗で滑りそうだった。後部座席では、赤ん坊の春人がぐずり始める。助手席の稽古は淡いピンクのカーディガンを整え、疲れた笑みを浮かべた。
「私、トイレに行ってくるわ。
春人、お願いね」
その声は穏やかだった。だが、十分が過ぎ、二十分が過ぎても、稽古は戻らない。
太郎は春人を抱え、女子トイレ前で妻の名を叫んだ。振り返る人々の目が冷たい。だが、恥など構っていられなかった。
「稽古! 稽古田中稽古!」
中を確認してくれた中年女性は首を振った。洗面所にも個室にもいない。
太郎の背筋を、ぬるい恐怖が這い上がる。
そのとき携帯が震えた。稽古からのメッセージだった。
――「実家に持っていくお土産、家に忘れたみたい。先に帰ってて。明日、私も向かうから」
文章は丁寧だが、どこか機械的だった。
さらに不可解なのは“忘れたみたい”という言い方だ。稽古は几帳面で、確認を怠る人間ではない。しかも、お盆当日に東京へ戻る? 渋滞の中を? あり得ない。
電話は繋がらず、電源が落ちたまま。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=RdNQTzKT6xA,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]