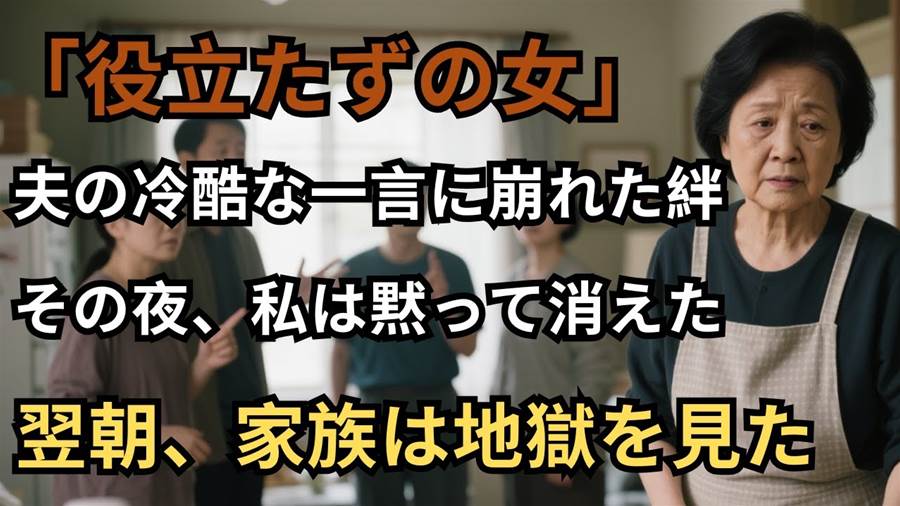「義母さんの席はないですよw」――その一言が、老舗料亭の静寂を切り裂きました。今日は息子・拓哉の昇進祝い。夫の正則と私は、創業百年の料亭に着物を新調して臨み、女将にも丁重に迎えられていたのです。
ところが座敷に通されると、名札の並ぶ席に私たち夫婦だけが見当たらない。女将が青ざめて「手違いで……」と口を開いた瞬間、嫁の里穂が小さく笑い、わざとらしく肩をすくめました。
「だって最近、家族行事にお呼びしてませんし。空気、読んでください」
拓哉は視線を逸らし、何も言わない――その沈黙が、答えでした。
胸の奥で、三十八年分の記憶が音を立てて崩れていく。学費、結婚資金、新居の頭金、孫の世話。尽くしても、最後に残ったのは「席はない」という宣告。私は怒りより先に、奇妙な冷静さに包まれました。
「女将さん、ご迷惑をおかけしました」
そう言って一礼し、席を立ったのです。
すると背後で、椅子が擦れる音が続きました。妹が立ち上がり、叔父が立ち上がり、従兄弟たちも次々と。やがて親戚三十人が、まるで示し合わせたように声を揃えます。
「会長が帰るなら、俺たちも帰る」
里穂の顔から血の気が引きました。「……会長?」と、乾いた声が漏れる。
女将も深く頭を下げました。実は私は、地域の文化団体で長く茶道の会を束ねてきた者で、この料亭とも二十年来の付き合いがある。今日招かれていた“会社の奥様方”の多くも、私の門下でした。里穂が「古い義母」と切り捨てた相手が、誰に支えられてきたのか――その現実が、畳の上で一気に露わになったのです。
玄関へ向かう私の背に、拓哉の上司が重い声を落としました。
「拓哉くん……今日は失礼する。後日、話がある」
祝いの席は、彼の信用を削る場へと変わっていました。
外に出ると初夏の風が頬を撫でました。私は正則の手を握り返し、静かに言いました。
「もう、私の尊厳を席次で測る人たちに、人生を預けない」
その日、料亭に残ったのは数名だけ。けれど私の周りには、三十人の“追随”ではなく、三十年分の信頼が確かに残っていました。
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=IB87OZofaJA,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]