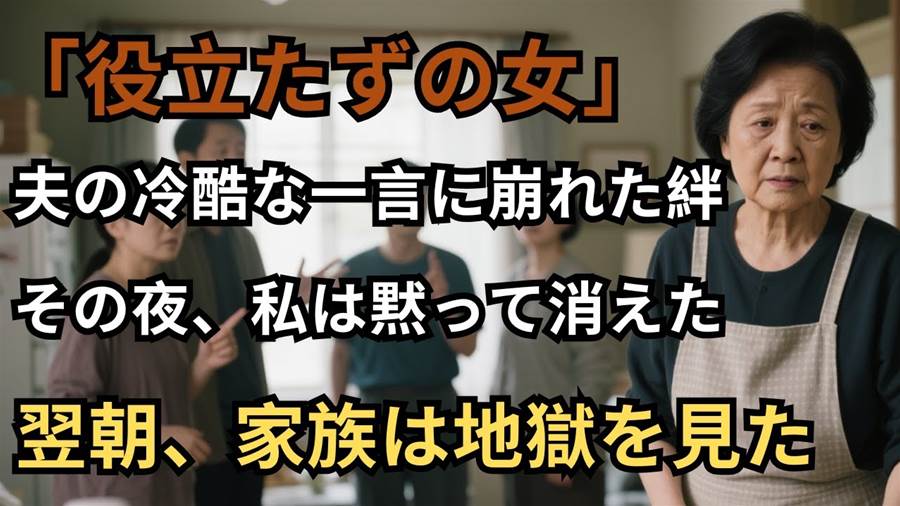「老後の面倒は見ない。それが俺たちの結論だ」
その言葉を、私は今でもはっきり覚えている。
あの日、リビングで向かい合っていた息子の健一は、感情を交えない声でそう告げた。隣には、腕を組んだまま視線を逸らす嫁の理沙がいた。
私は佐藤文子、当時六十九歳。
夫を亡くして三年、年金と少しの貯蓄で慎ましく暮らしていた。息子夫婦に金銭的な援助を求めたことは一度もない。それでも彼らは言った。
「将来の介護とか、正直無理だから」
「お母さんの人生は、お母さんで何とかしてほしいんです」
拒絶の理由は明確だった。
面倒を見たくない。ただ、それだけだった。
私は何も言い返せなかった。
その場では静かに頷き、二人を見送った。だが玄関の扉が閉まった瞬間、胸の奥で何かが音を立てて崩れ落ちた。
それから、息子夫婦とは完全な絶縁状態になった。
電話も手紙も来ない。こちらから連絡することもやめた。
数年後――。
私は七十五歳になっていた。
体は衰えたが、頭はまだはっきりしている。ひとりで暮らすには不安もあったが、地域の高齢者向け住宅へ移り、静かな生活を送っていた。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=yh9dHsIcHfs,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]