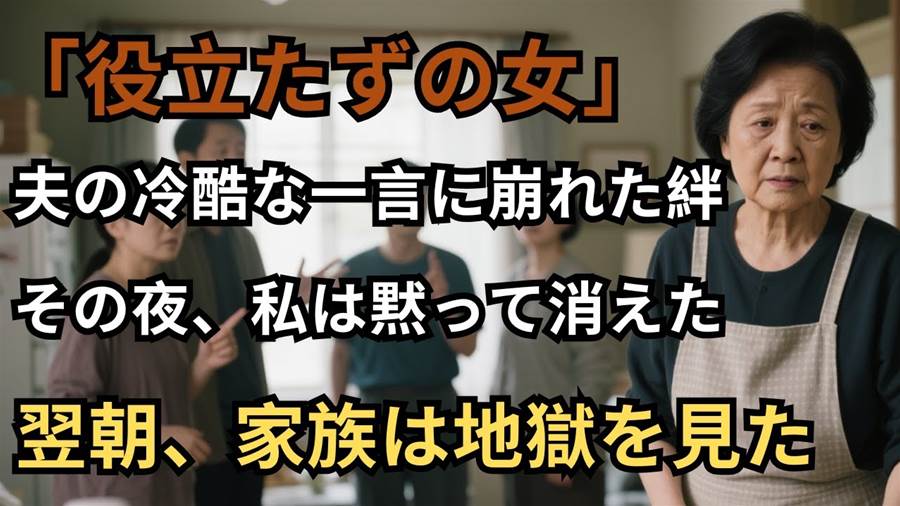夜のバスターミナルは、雨上がりの湿った空気と、消えかけた電光掲示板の光だけで成り立っていた。最終便の案内が淡々と流れるなか、長椅子の端に、二つの小さな影が並んで座っている。兄の蓮は、濡れた前髪の隙間から周囲を警戒し、妹の凛は、胸元のペンダントを握り締めた。母が遺したネックレス。金属の冷たさだけが、今も確かに「帰る場所があった」ことを思い出させる。
二人は天才と呼ばれてきた。蓮は数学と暗号解析に、凛は記憶と読解に異常なほど長けている。だが、その才能が彼らを守ったことは一度もない。母が亡くなり、後見人となった叔母・美佐子が笑顔で差し出した手は、保護ではなく管理の手だった。資産と権利、そして母の研究資料。美佐子の視線がそれらに向いていたことを、双子は遅れて理解した。
「迎えに来るって言ったのに……」
凛の声はかすれていた。約束の時間はとっくに過ぎている。スマートフォンの画面は圏外を示し、連絡先には「叔母」の名だけが残っている。蓮は、端末のログを何度も確認した。メッセージは既読になっていない。だが、それが「見ていない」のではなく「見せられていない」可能性を、彼は計算していた。
そのとき、背後から足音が近づき、黒いコートの男が立ち止まった。男は双子を一瞥し、何気ない口調で問いかける。
「子どもだけか。家は」
蓮は答えない。凛の指先がネックレスに触れ、反射的に首元を隠した。その仕草を見て、男の視線が一瞬鋭くなる。次の瞬間、男の携帯が鳴り、彼は短く「はい」と応じた。会話の断片が耳に刺さる。「確保」「首飾り」「今夜中に」。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=5UT827rsWKA,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]