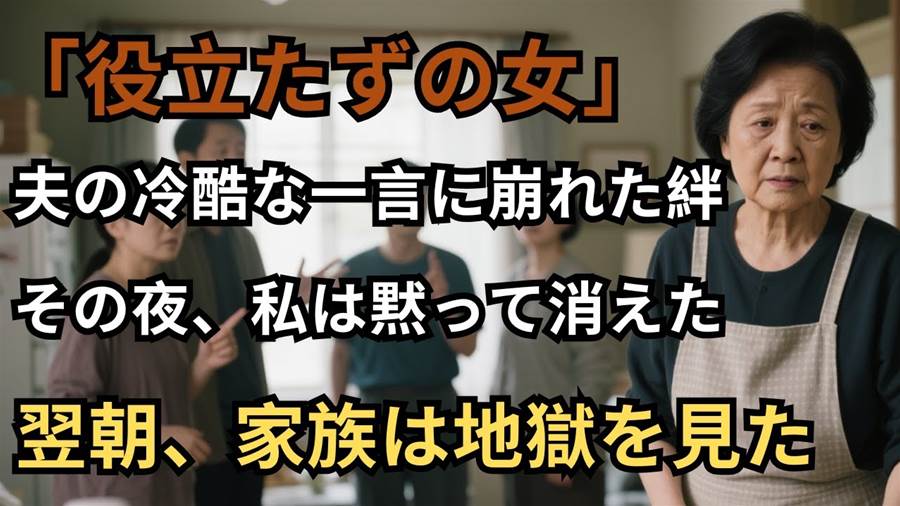「お母さんはもう、待ちきれなかった」――受話器の向こうで、72歳の母の声がかすかに震えていた。その震えは、怒りでも不満でもなく、長い孤独の底からにじみ出た静かな叫びだった。長野県・松本市郊外の古い一軒家。昼間でもひんやりと冷たい居間で、母は一人、時計の針が刻む小さな音だけを聞いていた。庭の紫陽花は今年も見事に咲いたのに、それを見守る人影はない。
東京で働く娘は電話越しに「忙しいから」と笑うだけ。その笑い声を胸に抱えたまま、母はまた一日を終えていた――。
その家は、築年数を重ねた木造の一軒家だった。障子越しに差し込む光は柔らかく、畳にはかすかない草の香りが残る。居間の隅には、娘が幼い頃に使っていた小さな机がまだ置かれていた。壁には家族写真が並び、笑顔の娘が父と母に挟まれている。しかし今、その家に響くのは時計の音と、時折風に揺れる庭の木々だけだった。
東京で働く一人娘は、いつも「今月は無理」「仕事が立て込んでいて」と帰省を先延ばしにしていた。電話では優しく話し、母の体調を気遣う言葉も忘れない。それでも、実際に顔を合わせるのは一年に一度あるかないか。
母はそれを責めず、ただ「元気ならそれでいい」と笑って受け止めてきた。
ある日、母から突然の電話が鳴った。
「めまいがして、立てないの…」
その一言に、娘は血の気が引いた。仕事も家事もすべて後回しにして、新幹線に飛び乗り松本の実家へ向かった。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
引用元:,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]