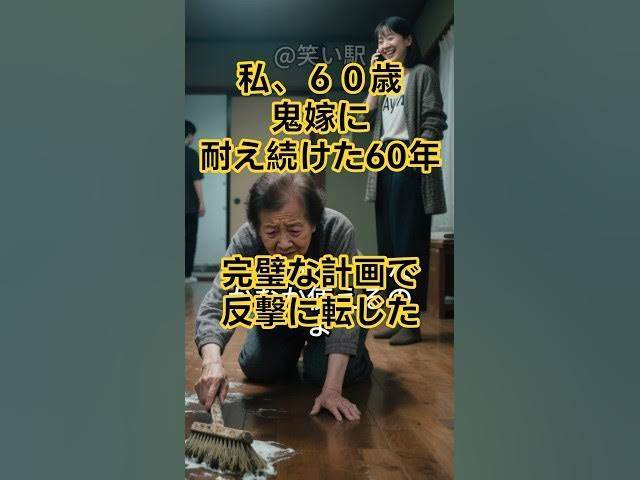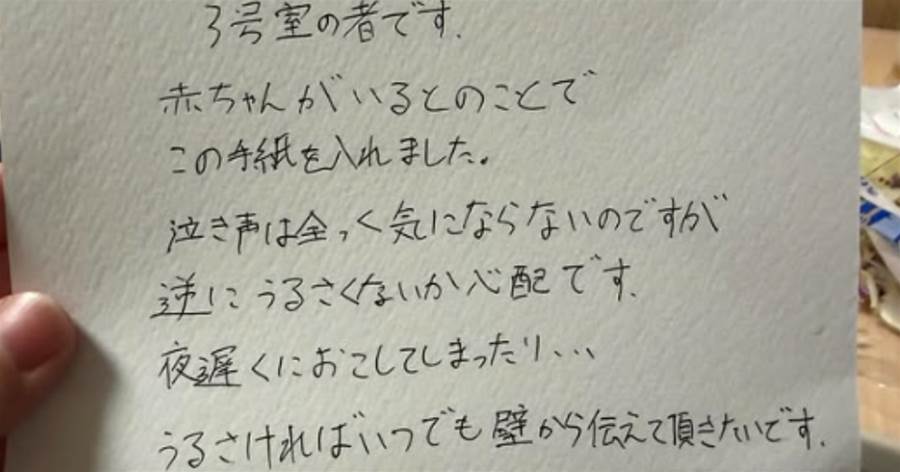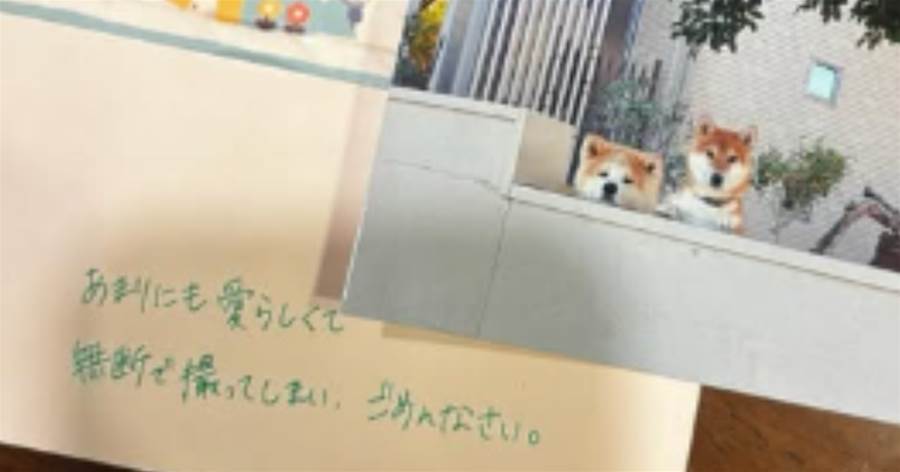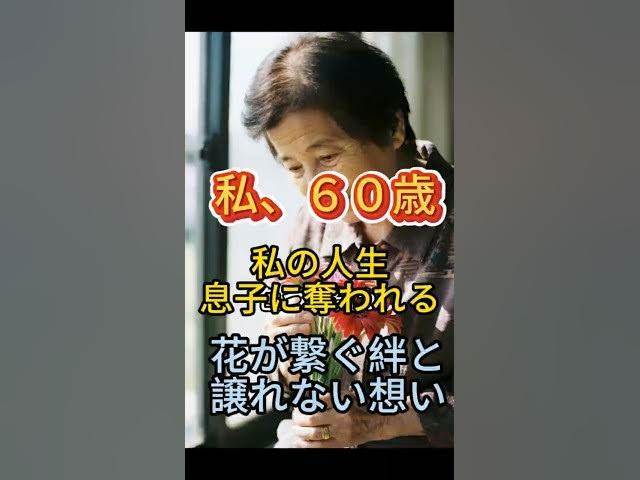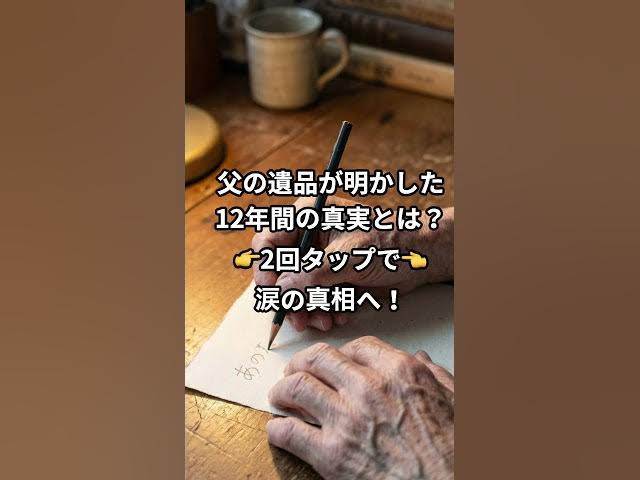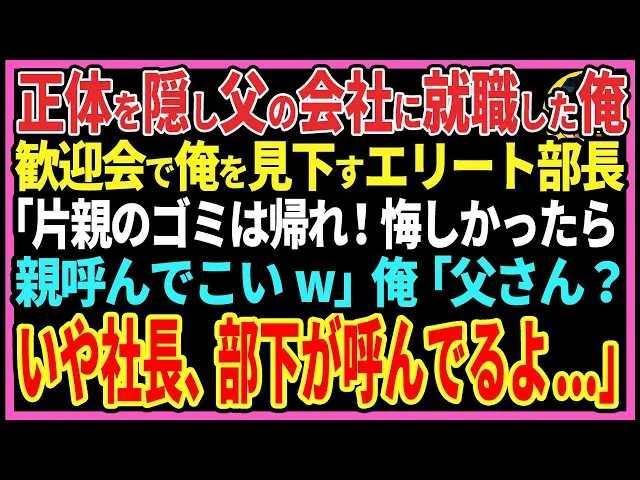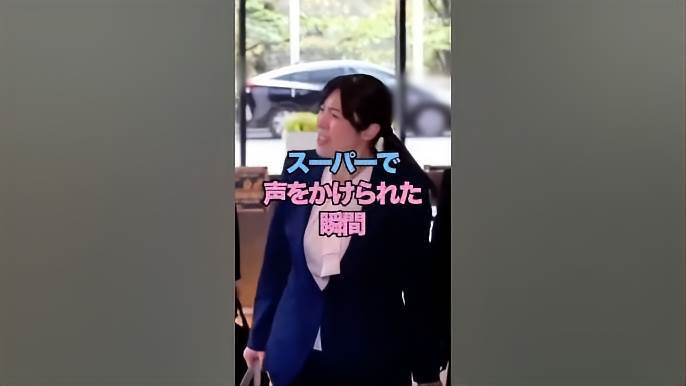2011年3月11日、未曾有の大災害が日本を襲った東日本大震災。その混乱と悲しみのさなか、一枚の写真が静かな波紋を広げました。災害派遣にあたっていた自衛隊員が、缶詰の「赤飯」を食べている姿です。
お祝いの席で食べられることの多い赤飯。我が家が、故郷が、全てがめちゃくちゃになったこの状況で、なぜ彼らはそんなものを食べているのか。
「災害がめでたいのか?不謹慎だ!」—そんな非難の声が、一部の被災者から上がりました。
しかし、その裏には痛ましい誤解がありました。当時、自衛隊は被災者に温かい炊き出しを優先的に届け、自分たちは人目を忍んで冷たい缶詰で空腹を凌いでいたのです。赤飯が支給されたのは、祝いのためではなく、「腹持ちが良く、栄養価が高いから」という極めて実用的な理由からでした。それでも、この誤解は不信を招き、その後、災害派遣時に自衛隊員へ赤飯を配らない方針へと変更されるきっかけとなってしまいました。
しかし、同じ赤飯をめぐり、全く別の心温まる出来事も記録されています。
震災からしばらく経った頃、避難所となっていたある小学校の保護者から、自衛隊に一つの願いが寄せられました。
「卒業式を行いたいが、何も残っていない。せめて子どもたちを祝ってやりたいので、赤飯を分けてもらえないか」。この申し出に、部隊の指揮官は喜んで応じ、子供たちの門出のために赤飯を渡したといいます。不謹慎の象徴と見なされた赤飯が、未来への希望の象徴となった瞬間でした。
人間の心理の複雑さを示すエピソードは、これだけではありません。
被災地では、あるファミリーレストランの運営会社が、数ヶ月にわたり無償で炊き出しを続けていました。当初、温かくしっかりとした食事に誰もが涙を流して感謝しました。しかし、支援が日常になると、人の心は少しずつ変化していきます。一週間も経つ頃には、「またファミレスのメニューか…」と愚痴をこぼす声が聞こえるようになったとも言われています。
人は、当たり前になった優しさや、あまりにも長く続く支援に対し、感謝の気持ちを忘れがちになるのかもしれません。極限状態の中で見えた、人間の複雑な一面を物語るエピソードです。