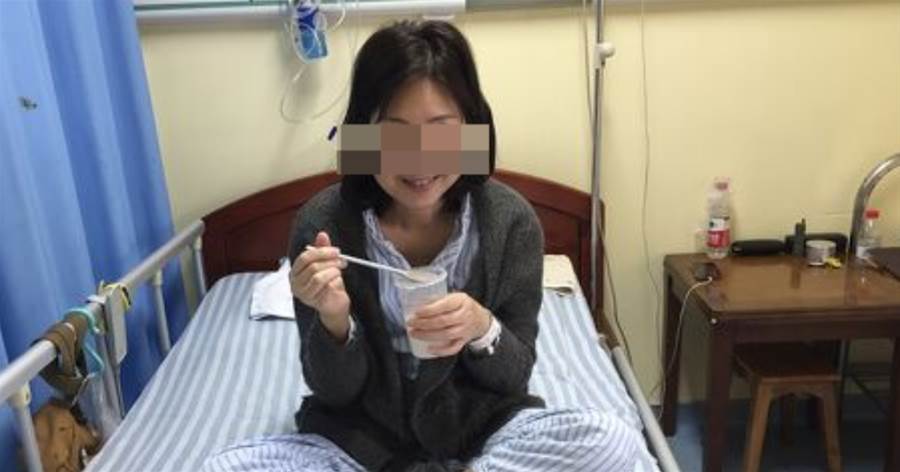
入院の手続きが終わった夜、病室の天井は白く、時計の針だけが妙に大きく響いていた。点滴の雫が落ちる音を聞きながら、私はスマートフォンを握り締めていた。息子に「大丈夫よ」と伝えたかった。息子の手を煩わせたくなかった。けれど胸の奥には、別の不安が沈んでいた。
嫁の真紀は、結婚当初から淡々としていた。礼儀はある。言葉遣いも丁寧だ。
だが、家の空気だけはいつも冷えたままだった。私は夫を亡くしてから、息子夫婦の家に身を寄せていた。遠慮しているつもりだった。家事もできる範囲でやり、生活費もできるだけ出した。迷惑にならないようにと、ずっと気を張ってきた。
それでも、入院が決まった日の真紀の言葉は、刃物のようにまっすぐだった。
「お義母さん、これを機に実家に戻るとか、施設とか、考えてもらえませんか」
息子は曖昧に笑って、「今は病気が先だろ」と言ったが、止める強さはなかった。私はその場で何も言い返さなかった。言い返すほど、私はもう若くなかった。体が先に折れてしまう。
入院して三日目、真紀から短いメッセージが届いた。
「帰ってこなくていいよ」
たったそれだけ。理由も説明もない。私は一瞬、文字の意味が理解できなかった。指先が冷たくなり、血が引いていくのを感じた。すぐに息子へ電話をかけた。呼び出し音の後、息子の声が出た。
「母さん……今、話しにくい」
その声の向こうで、誰かの話し声がした。聞き慣れない男性の低い声。次に女性の笑い声。私は胸騒ぎを覚えた。
「誰がいるの」
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください



















