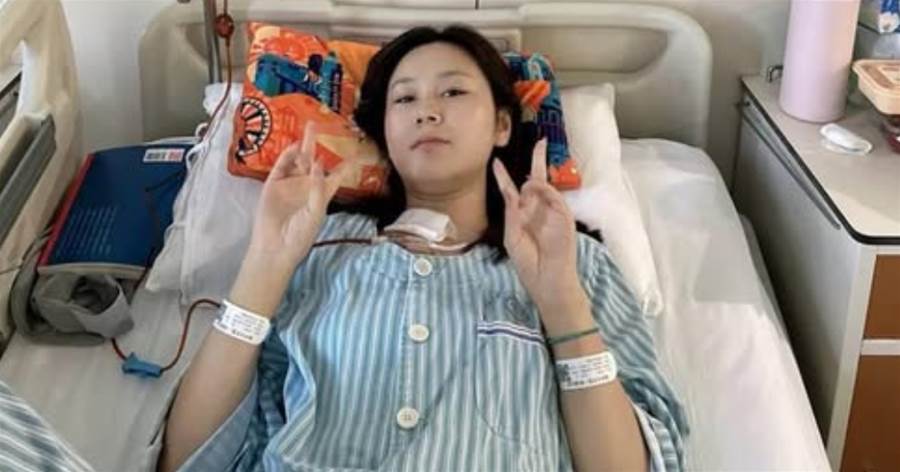深夜1時。突然、家の中に響き渡る大きな音で目が覚めた。心臓が喉から飛び出しそうなほど、嫌な予感がした。寝室のドアを開けた瞬間、そこには言葉では表現できない光景が広がっていた。床一面に吐しゃ物が広がり、夫がその中に倒れていた。服は汗でびっしょりと濡れ、手足は氷のように冷たく、まるで命を失っているかのような姿だった。
隣の部屋では、4歳の娘が何も知らずに眠っていた。
無邪気な寝顔を見て、私は何とかその場で冷静さを保とうとした。しかし、目の前の現実はあまりにも無情で、冷静でいられるはずもなかった。
夫は必死に言った。「大丈夫……ちょっと寝れば治る……」その言葉がどれだけ虚しく響いたことか。唇は紙のように白く、全身から冷や汗が流れている。何よりも、彼は失禁していた。それを見た瞬間、私は確信した。「これは絶対に“大丈夫”じゃない。」
瞬時に、私は119に電話をかけた。電話の向こうで、落ち着いた声で次々と質問が続いた。「今の症状は?」「持病はありますか?」泣きながら答えながらも、その時私はまだ気づいていなかった。心筋梗塞の「黄金の時間」が、あの一問一答で確実に削られていくことを。
数分後、救急隊から折り返しの電話がかかってきた。最初の一言が、「どちらの病院に搬送しますか?」だった。その瞬間、私は一瞬頭が真っ白になった。「これは選択肢ではない。生死を分ける分岐点だ。」私は叫んだ。「市内の総合病院へ!お願いします、早く!」後で知ったことだが、この判断が夫の命を救ったのだ。もし「胸痛センター」を持っていない病院だったら、即座に治療は始まらなかっただろう。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください