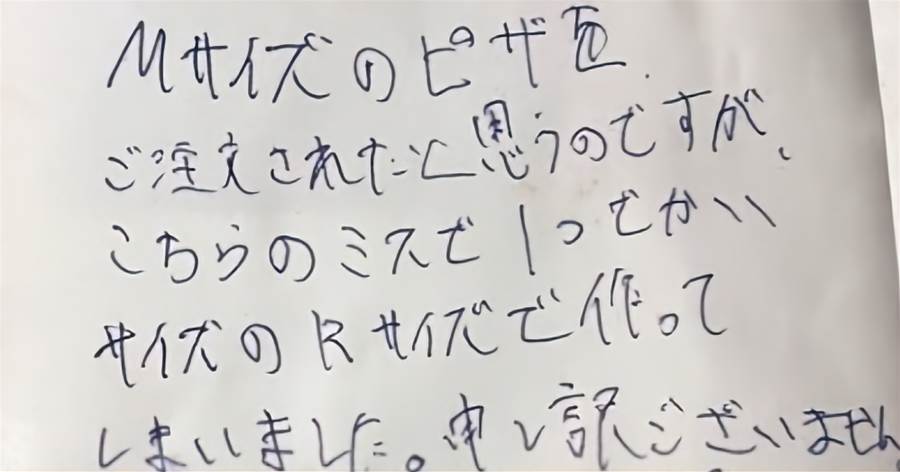陣痛が始まったのは、夜明け前だった。腹の奥がぎゅっと絞られ、間隔を測ると確実に短くなっている。私は深呼吸しながらスマホを握り、まず夫に電話した。だが出ない。出張中だと言っていたのを思い出し、次に頼れる相手として義母へ連絡した。
「すみません……陣痛が来ました。病院まで車で送っていただけませんか」
電話口の義母は、妙に機嫌が良かった。
眠気よりも、面白がるような声が混じっていた。
「はぁ?救急車でも呼べば?まあ、仕方ないわね。今行くわ」
十分ほどで義母の車が家の前に停まり、私は陣痛の波に耐えながら助手席へ滑り込んだ。シートベルトを締める指先が震える。義母は運転席で、まるで買い物に出るような軽い調子だった。
走り出して数分。私は痛みで声が出せず、窓の外の街灯が流れていくのをただ見つめた。ところが、車は病院方向ではなく、なぜか郊外の細い道へ入っていった。
「……道、違いませんか」
私が絞り出すように言うと、義母は笑った。
「近道よ。静かにしてなさい」
しかし近道にしては暗すぎる。民家も少なく、道端には雑草が伸びている。
嫌な予感が背中を伝った。すると義母は突然ウインカーを出し、路肩に車を寄せて止めた。
「降りなさい」
「え……?病院は……」
義母は私の方を見もせず、薄く笑って言った。
「甘えず自力で行けw」
次の瞬間、ドアロックが解除され、私は半ば押し出されるように外へ出た。義母は窓を少しだけ開け、最後に一言だけ投げた。
「歩けばいいでしょ。若いんだから」
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください