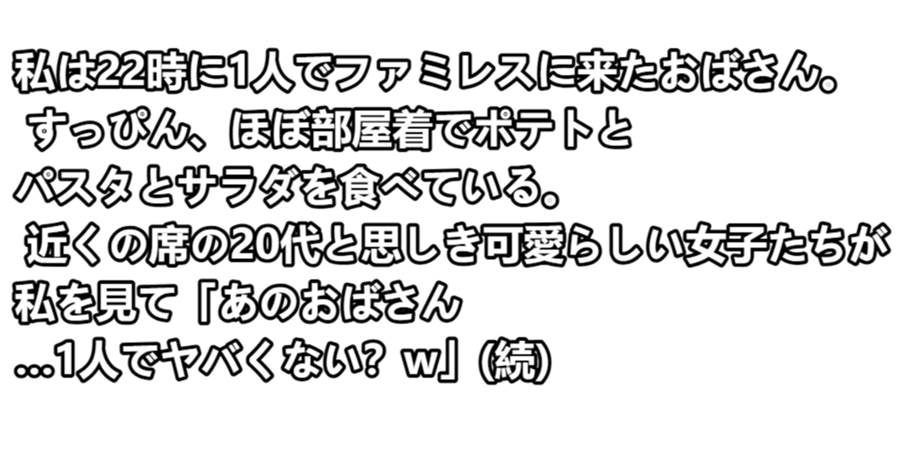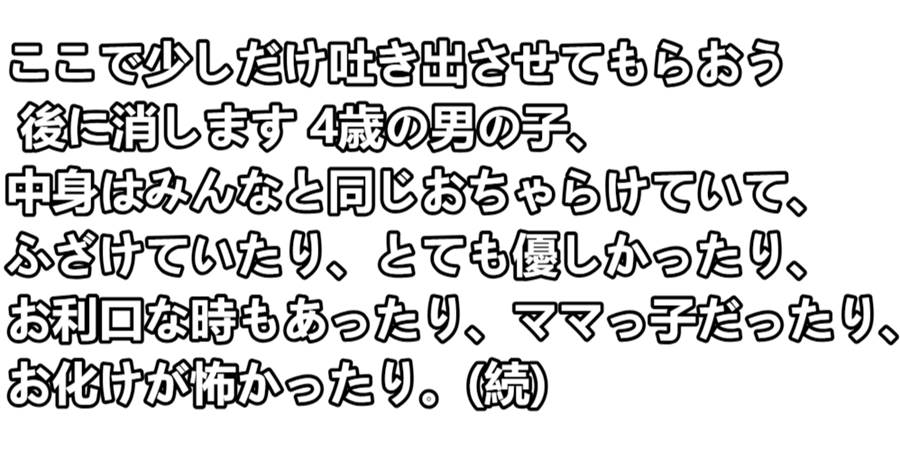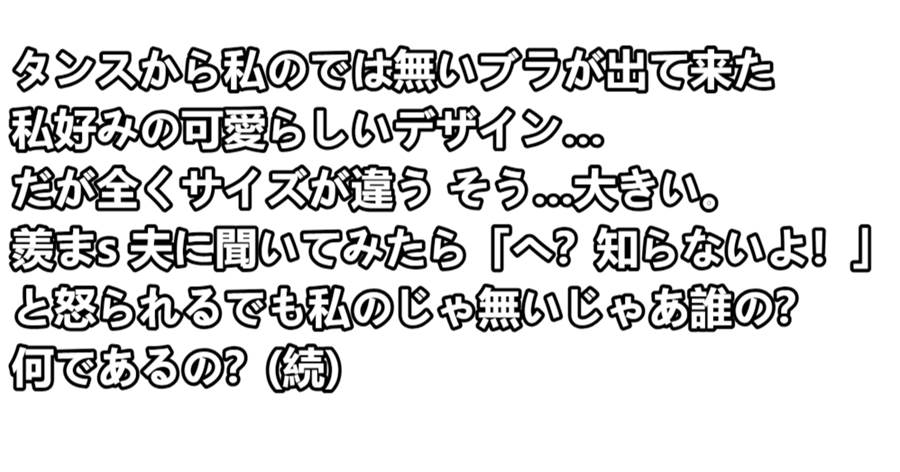十一年という時間は、いつの間にか生活の隅々に染み込みます。私にとってそれは、毎朝同じ時刻にエンジンをかけ、夫を駅まで送るという習慣でした。誰に頼まれたわけでもありません。結婚した当初、夫が「会社まで遠いし、駅まで歩くのはきつい日もある」と笑ったのをきっかけに、私が自然にハンドルを握るようになったのです。
季節が巡り、道の混み具合も、駅前の景色も変わりました。
それでも、私の朝は変わりませんでした。朝食の片づけを急いで終え、夫の忘れ物を確認し、車の鍵を手に取る。助手席のシートにはいつも同じ角度で夫の鞄が置かれ、私は何度も同じ信号で同じ車列に並びました。十一年分の「いつも」が、そこにありました。
その日も同じように始まったはずでした。ところが、空は不意に色を変え、駅に着く頃には雨が本気を出したように叩きつけてきました。傘を持たない夫は、改札へ小走りで向かうしかなかったのでしょう。仕事終わりに迎えに行ったとき、夫は少し息を切らして助手席に滑り込みました。
「ありがとう!待たせてゴメン。急に雨降ってきて大変だったよ」
明るい声。申し訳なさそうな笑顔。
いつもと同じ、私が守ってきた“夫の表情”でした。私は「うん」とだけ返し、視線を前に固定したまま発進します。ワイパーがリズムを刻み、車内は雨音で満たされました。
次の瞬間、私の視界の端に、夫の足元が入ったのです。濡れた靴。泥の跡。雨水を吸った靴下のにおいまでが、妙に生々しく伝わってきました。
それは、ただの雨のせいではありませんでした。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください