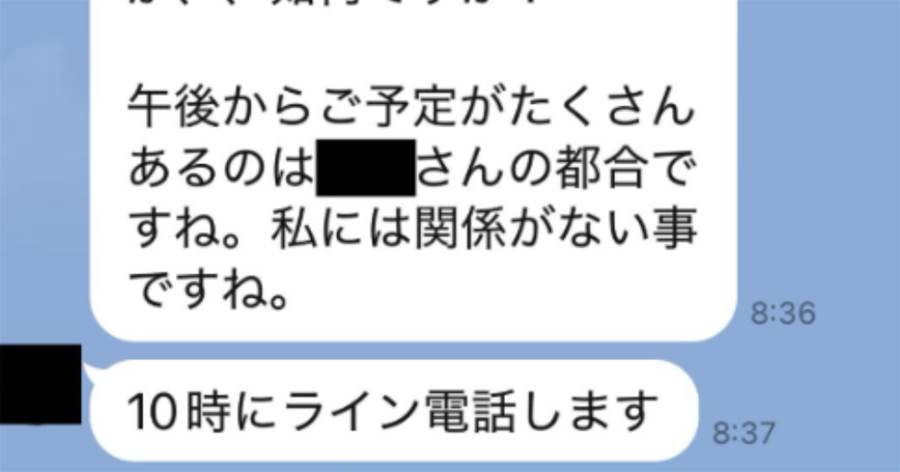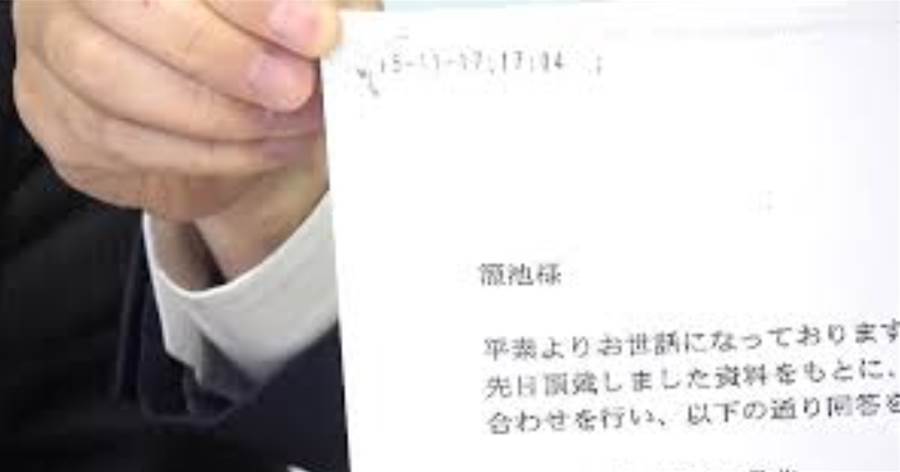「この子、もういらないんです。」
雪が舞い始めた静かな冬の午後、老舗料亭「春日庭(かすがてい)」の玄関先で、その言葉は冷たい刃のように落ちた。差し出されたのは、やせた身体に大きめのコートを着た小さな少女。膝元は濡れ、前髪が半分、顔を隠している。それでも目だけは真っすぐで、私――若旦那の大輔の顔を、逃げずに見つめていた。
付き添いの遠い親戚の女性は、目を伏せたまま続けた。
「手先は器用なんです。でも、気持ちがないみたいで怖いくらいで。家でも全然話さないし、空気も読めないし……正直、育てきれません」
そして、ため息まじりに付け加える。
「料理だけは覚えが早いので……使い道があるかもって」
使い道。子どもを物のように言うその口ぶりに、胸の奥がざらついた。少女――花は、うつむきもしない。いらない、と言われても、何も返さず、ただ立っている。その姿が不思議と、昔どこかで見た光景のように感じられた。
人に必要とされないまま、感情をしまい込んで立っている子ども。
気づけば、私の口が動いていた。
「……しばらく、預かります」
親戚の女性は安堵したように頷き、花の肩を軽く押した。花は何も言わず、ただ静かに私を見上げた。そのまなざしが、何かを必死に我慢しているように見えて、私はその晩、何度も思い出すことになる。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=Pc0MhaJfS-o,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]