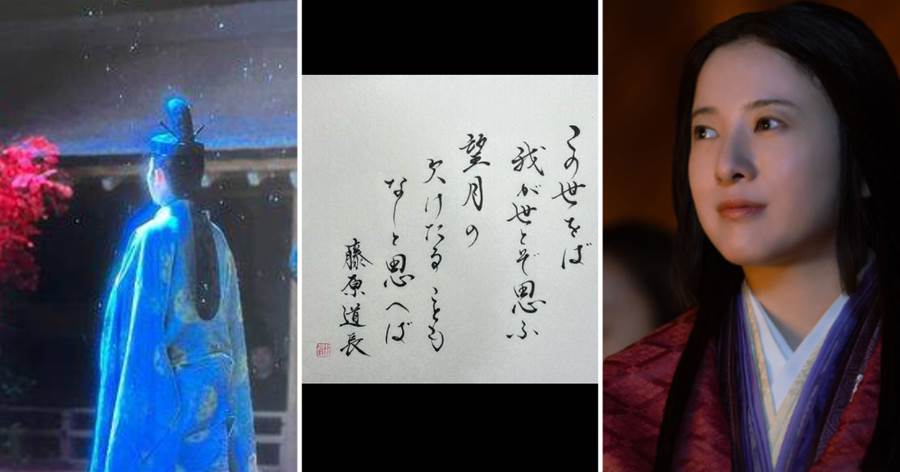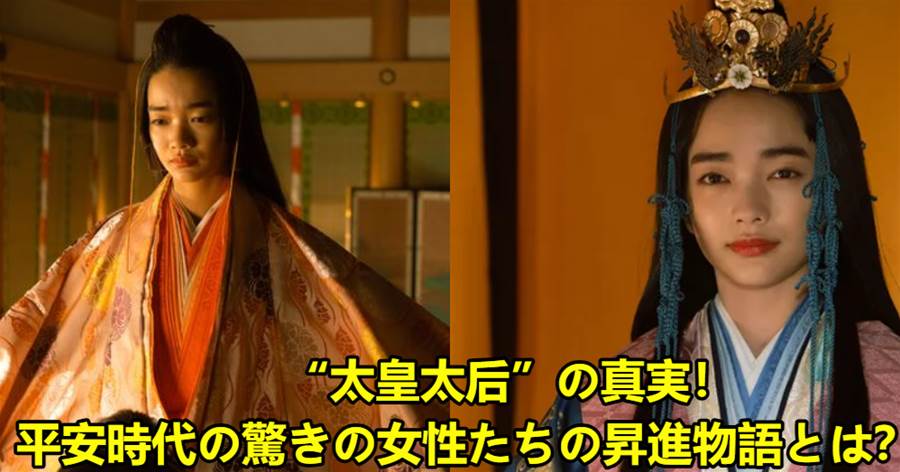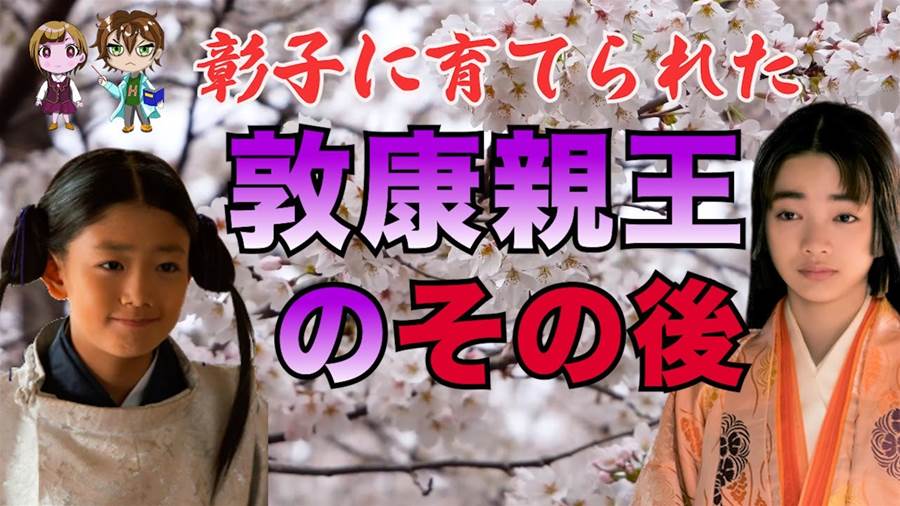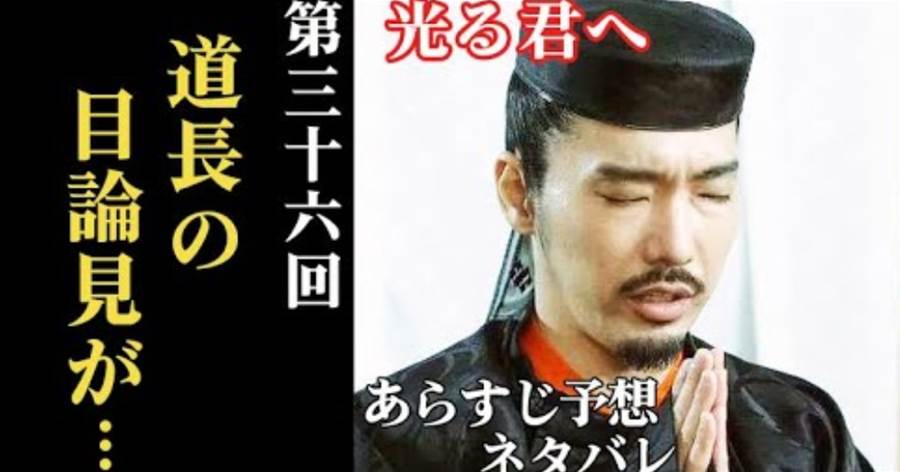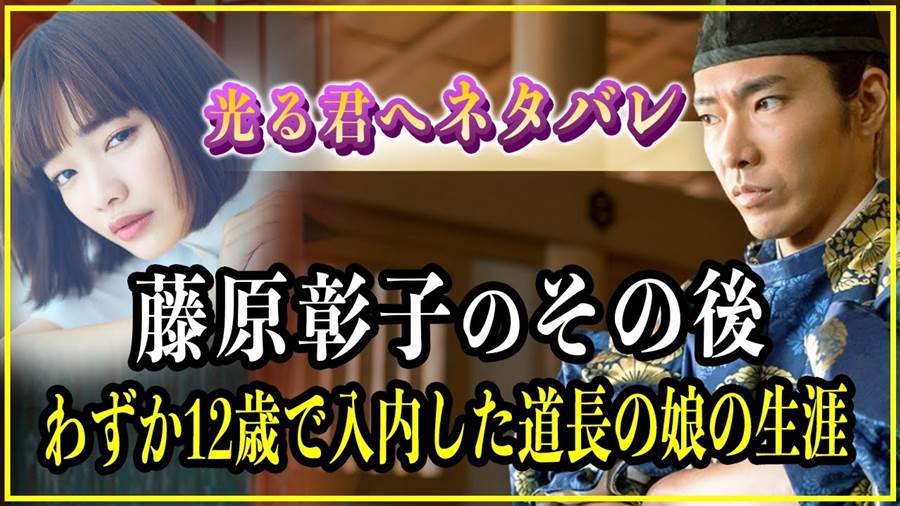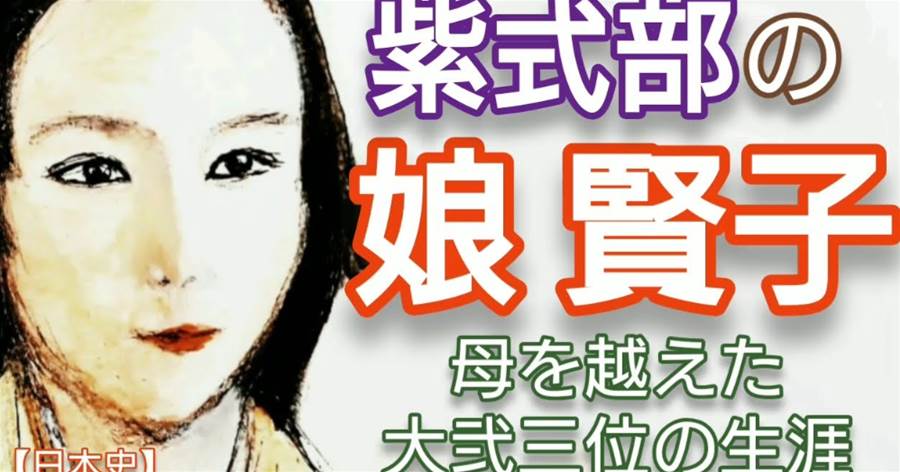
紫式部の名作『源氏物語』は、古今東西の文学愛好者にとって欠かせない作品ですが、その娘である藤原賢子(かたこ)の生涯は、彼女自身が歴史に名を残すほどのものでした。母を超えるほどの出世を遂げ、天皇の乳母として活躍した彼女は、どのようにしてその地位を築いたのでしょうか。
紫式部は、998年に藤原宣孝と結婚し、翌年に藤原賢子を出産しました。
しかし、その幸福は長く続かず、宣孝は1001年に病で亡くなります。母と娘は悲しみの中で支え合い、紫式部は後に『源氏物語』を執筆することで、その心の空白を埋めました。
一方で賢子は、幼少期から母の影響を強く受けて育ちました。文学的な才能や教養を身につける一方で、彼女は自らの道を切り開くための努力を惜しみませんでした。

18歳になった賢子は、母と同じく一条天皇の后、彰子に仕える女房として出仕しました。
当初、賢子は「源氏物語の作者・紫式部の娘」というプレッシャーを感じながらも、その名に恥じないよう努力を重ねました。彼女の才能はすぐに認められ、後に直線集に37首もの和歌が採用されるほどの地位を築き上げました。
しかし、賢子はただの「紫式部の娘」では終わりませんでした。彼女は数多くの男性貴族たちと知的かつ情熱的な交際を繰り広げ、その中で多くの経験を積み重ねていきました。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください