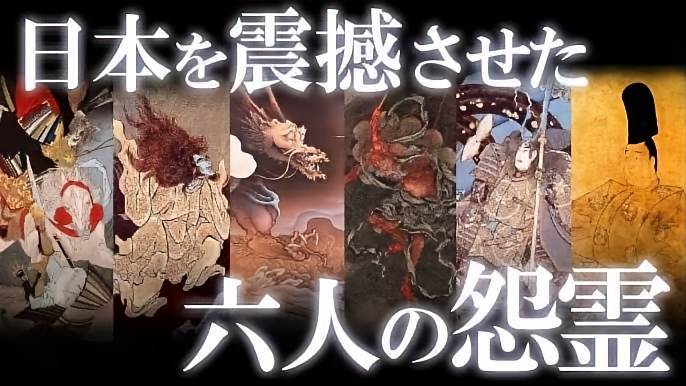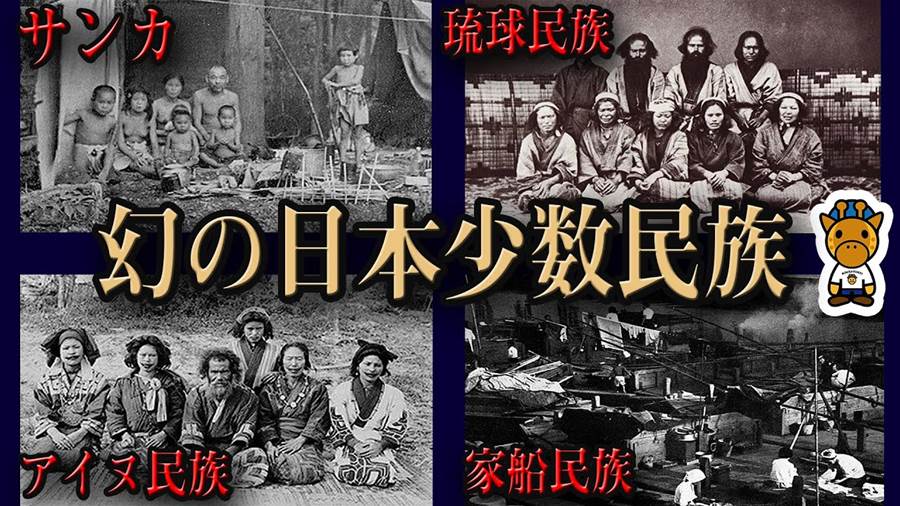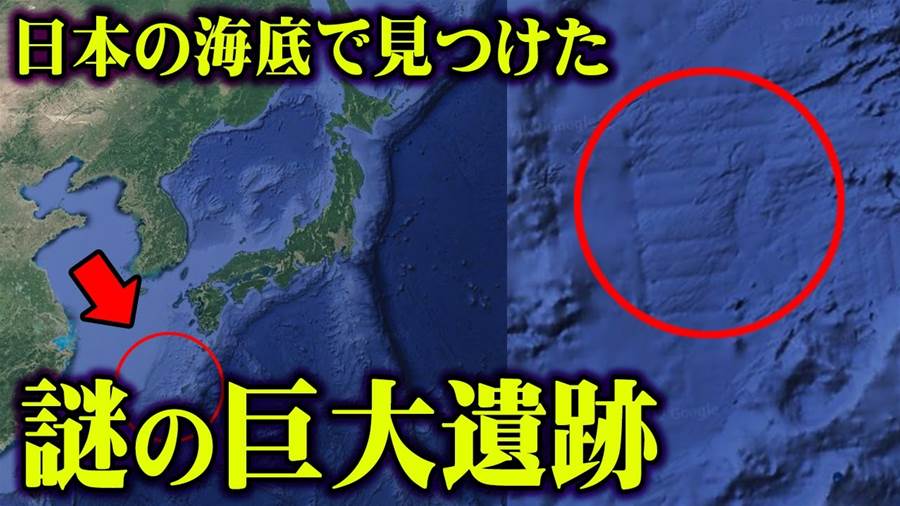日本の武士道とともに語られるのが、侍の腰に携えられた二本の刀。時代劇などでおなじみの光景だが、なぜ侍たちは二本の刀を身に着けていたのだろうか?その背後にある深い歴史と理由を紐解いてみよう。
まず、侍が刀を二本差している理由の根本には「武士の証」としての意味がある。武士たちは、「打刀(うちがたな)」と「脇差(わきざし)」の二本を常に携帯していた。
この二本を所持していることが、他の農民や商人と武士を区別する象徴となっていたのだ。

打刀は、主に戦場での戦闘に使用されるメインウェポンで、侍の魂とも言われるものである。戦国時代から江戸時代にかけて、侍たちはこの刀を自らの身分と名誉を守るために持ち歩いていた。一方、脇差は補助的な役割を持ち、特に近接戦闘や護身のために使われることが多かった。
打刀は、腰に直接差し、すぐに抜刀できるように作られた刀で、戦場での戦いに最適化されたデザインとなっている。
この刀の特徴は、反りが浅く、比較的軽量であることだ。これにより、徒歩での戦闘が主流となった戦国時代には非常に使い勝手が良かった。

脇差は、打刀に比べて短く、刀身の長さは1尺(約30cm)から2尺(約60cm)未満であることが一般的である。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください