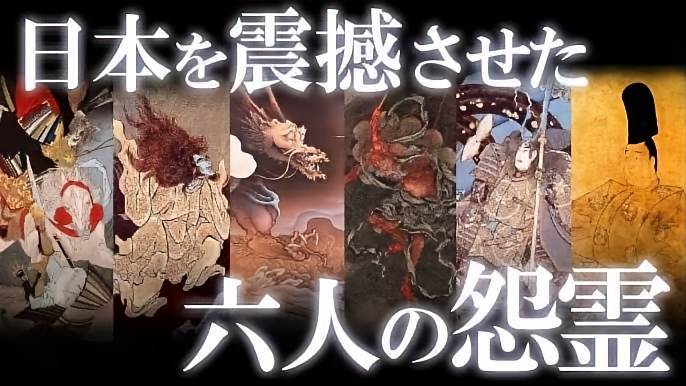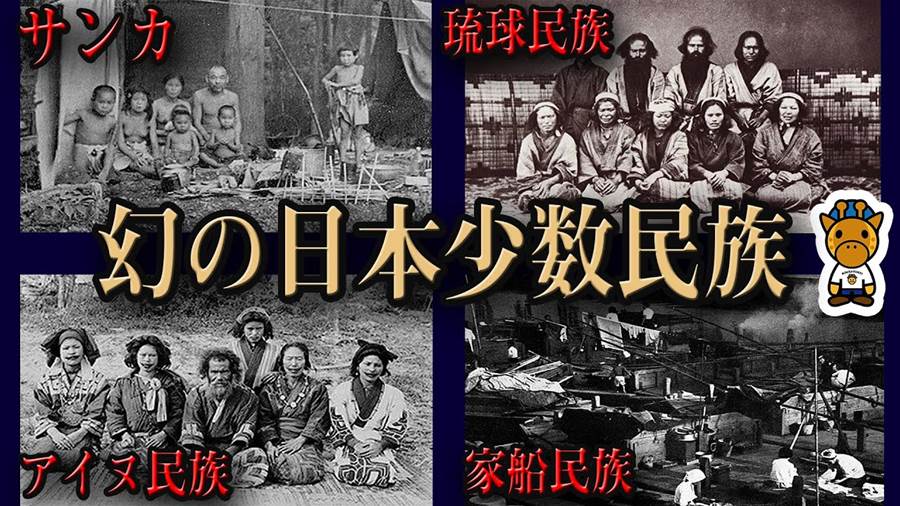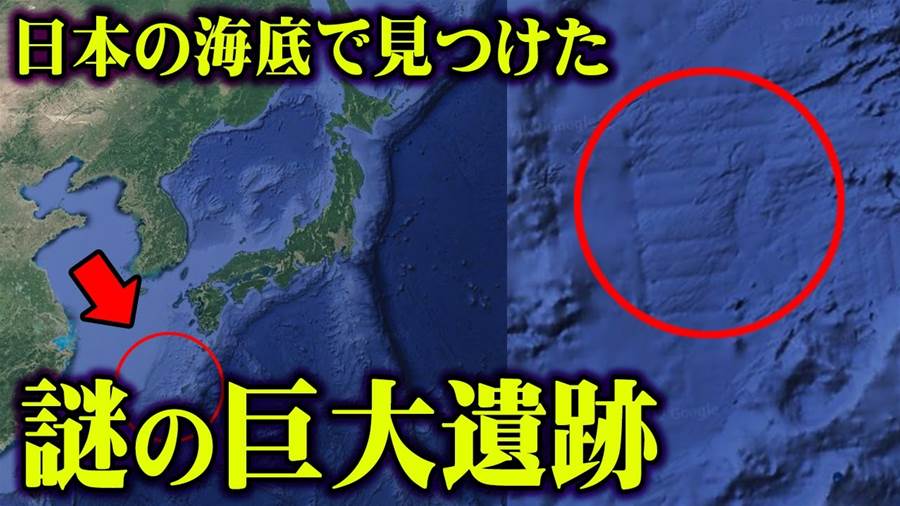中世ヨーロッパの騎士が盾と剣を駆使して戦う姿は多くの人が思い浮かべるところですが、日本の侍は違います。日本の侍は戦場で盾を持たず、むしろその代わりに日本刀を握りしめて戦いました。
まずは侍のルーツからおさらいしましょう。侍が登場したのは平安時代。元々は天皇や貴族に仕える者たちで、警護や奉公が主な役割でした。
しかし、時代が進むにつれて、戦が増え、武士としての役割が大きくなっていきました。特に鎌倉時代から室町時代にかけて、侍たちは戦場での戦闘が主な任務となり、その戦いぶりが後世に語り継がれるようになります。

では、なぜ侍は盾を使わなかったのでしょうか。実は、古代の日本にも盾は存在していました。縄文時代や弥生時代には、狩猟や戦闘において盾が使われていたことが確認されています。しかし、平安時代以降、盾は次第に使われなくなりました。
その理由の一つは、侍たちの主な武器である日本刀や弓矢が両手で扱うものであったことです。日本刀は重く、片手で扱うのは困難でした。また、弓を引くには両手が必要で、片手に盾を持つことは現実的ではありませんでした。
さらに、盾が使われなくなったもう一つの理由は、機動性の重視です。5世紀頃に馬が日本に伝来し、侍たちは騎馬戦を主とする戦闘スタイルを採用しました。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください