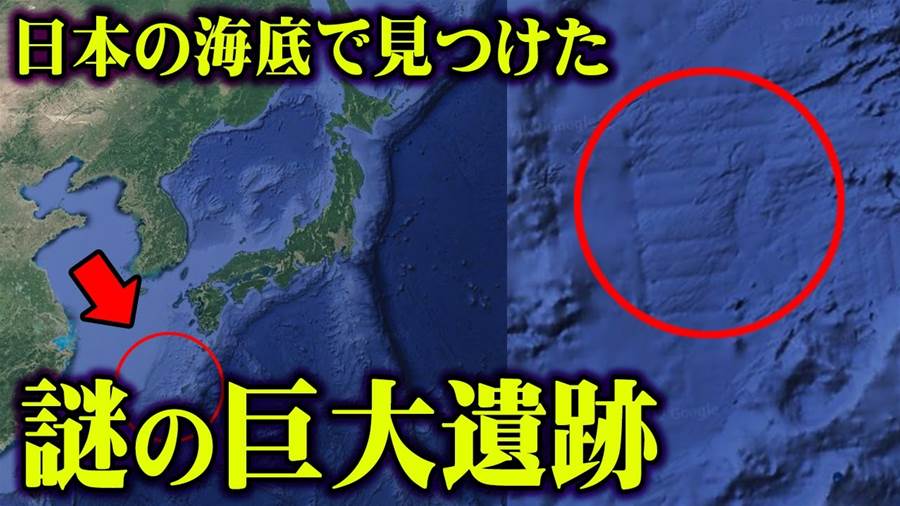草の匂い、油の匂い、そして、静かな風。その夜、鹿児島・知覧の飛行場には、翌朝の空を知る者たちの沈黙があった。
22歳の青年・渡辺静少尉。彼は出撃の前夜、整備士にこう言ったという。
「座席は、私の死に場所だから、手入れをたのむ」
その言葉を聞いた整備士は、しばらく動けなかった。若者の声は静かだったが、決して震えてはいなかった。

昭和20年6月6日。渡辺少尉は、爆装三式戦闘機「飛燕」に搭乗し、知覧基地を13時31分に離陸した。そのまま沖縄の洋上で連合艦船群へ突入。16時、彼の機体は消息を絶った。
その朝、出撃を控えた彼が、草むらの中で“あるもの”を胸に抱いている姿が撮影された。その写真が後に発見され、多くの人の心を揺さぶることになる。(※その“あるもの”が何であったのか——本文後半で明かされる。)
整備士たちは、彼の機体を送り出したあと、黙って空を見上げた。
空はあの日も、晴れていたという。
遺品の日誌「修養録」には、たった一首の句が残されている。
「いざ征かん雨も風をも乗越えて吾れ沖縄の球と砕けん」
その句を読んだ者は皆、息を呑んだ。潔さの中に、苦しみがある。死を恐れないように書かれたその筆跡の裏に、「生きたい」という叫びが滲んでいた。
後に発見された一枚の写真。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください