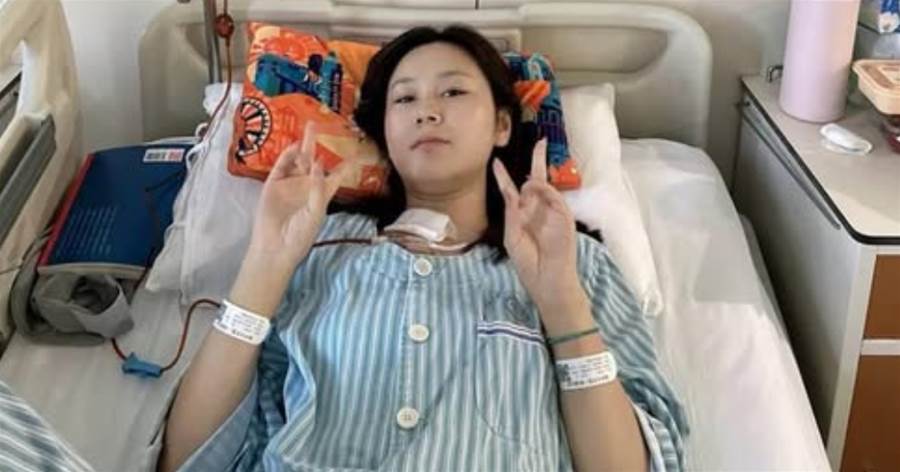昨日の夜、私は一生忘れられない夜を過ごした。決して大声で語りたいわけではない。ただ、胸の奥にずっと残って離れない思いがあるから、今、この言葉を綴らずにはいられなかった。
深夜、98歳のおばあさんが救急搬送されてきた。救急車の扉が開いた瞬間、冷たい夜の空気よりも、重い緊張が一気に流れ込んできた。診断は心筋梗塞。しかし、高齢のおばあさんの身体は、すでに限界に近い状態だった。
医師からの説明を聞いた娘夫婦は、静かに首を縦に振った。「延命治療は希望しません。自然に任せたいです。」声は震えていたが、その言葉には覚悟と、どうしようもない愛情が込められていた。
おばあさんは、施設で息苦しさを訴えていたにも関わらず、「どこも悪くない」と言っていたという。その強い意志は、長い年月を生き抜いてきた人に共通するものだろう。強く生きてきた人ほど、最後まで「大丈夫」と言おうとするのだ。
バイタルサインは安定していたものの、手足は冷たく、唇は薄く紫色になっていた。そんな異変に、嫌な予感だけが静かに広がっていった。
おばあさんの入院が決まり、着替えをしている途中、ほんの一瞬、呼吸のリズムが乱れた。
その瞬間、背筋がぞくっとした。長く働いていると、「言葉にならない変化」を肌で感じることがある。その予感は、間違いなく本物だった。
娘さんが医師に尋ねた。「弟は今すぐ来た方がいいでしょうか?」医師は時計を見て、静かに答えた。「深夜だから、明日でも大丈夫だと思いますよ。」確かに医学的には理にかなっていた。しかし、私の胸の奥で何かが叫んだ。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください