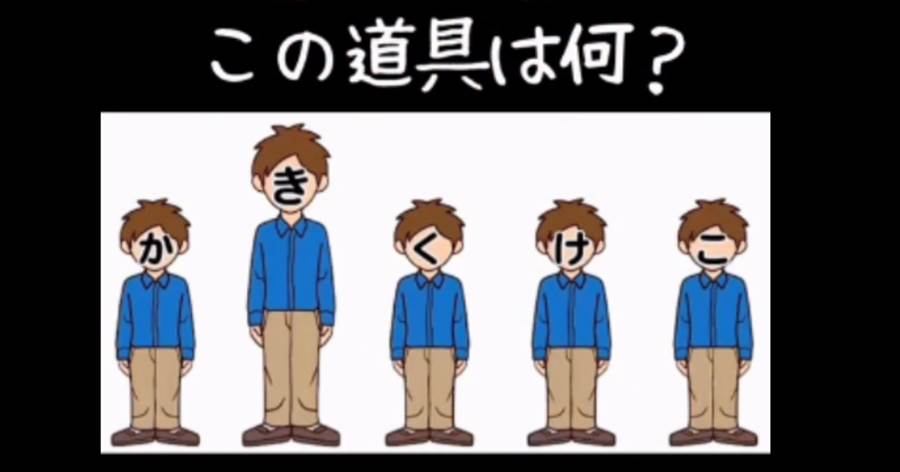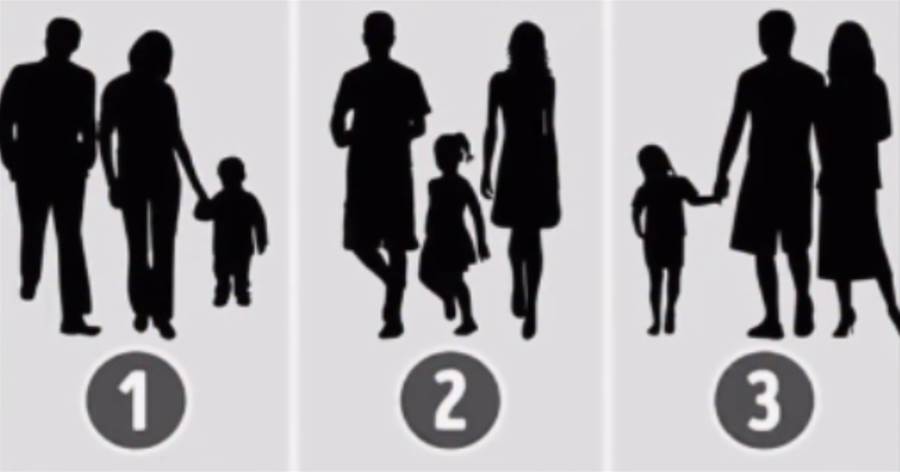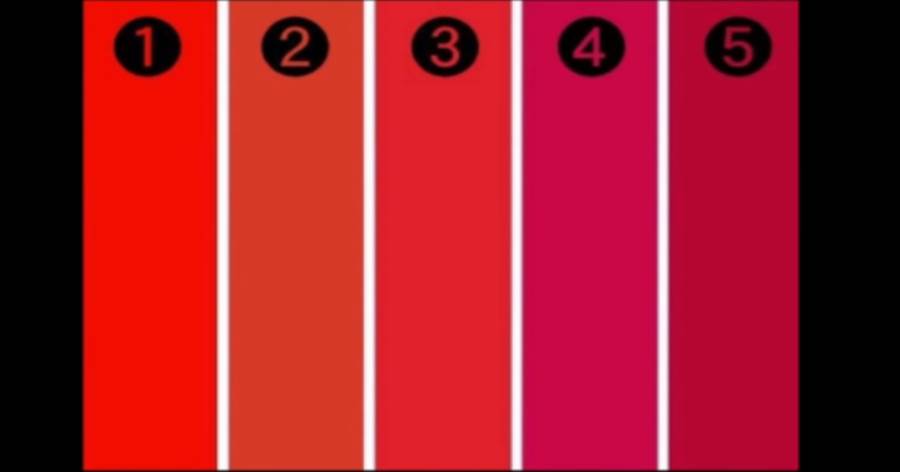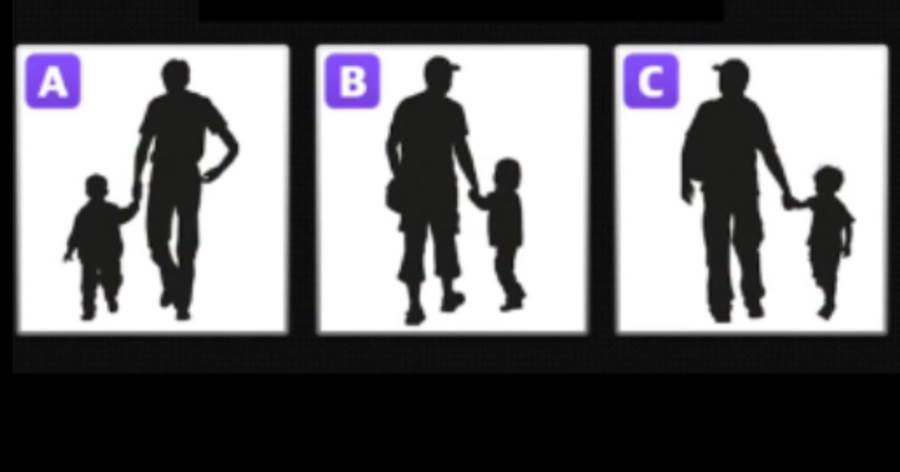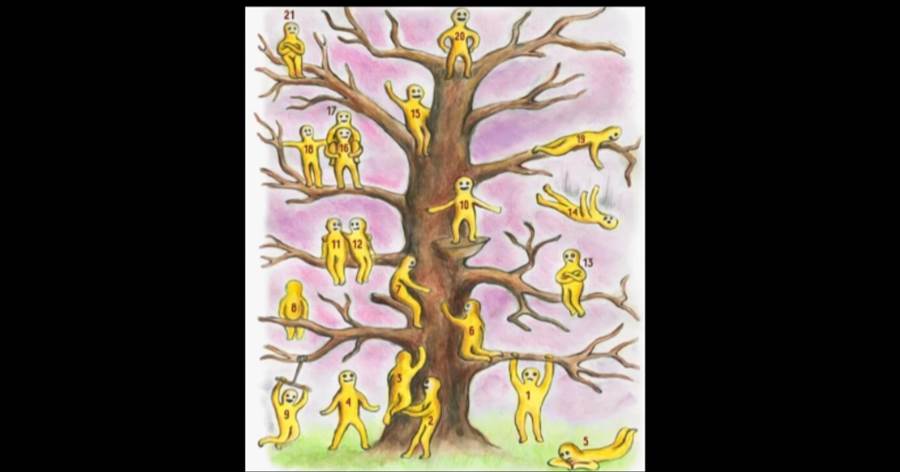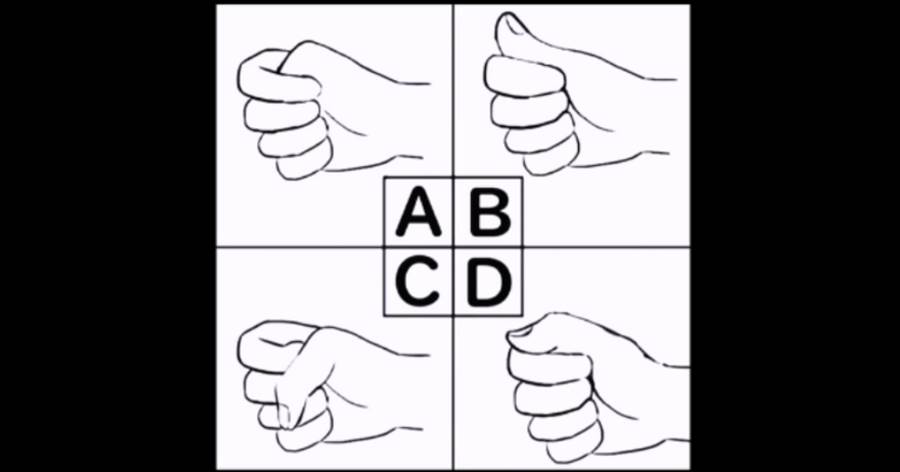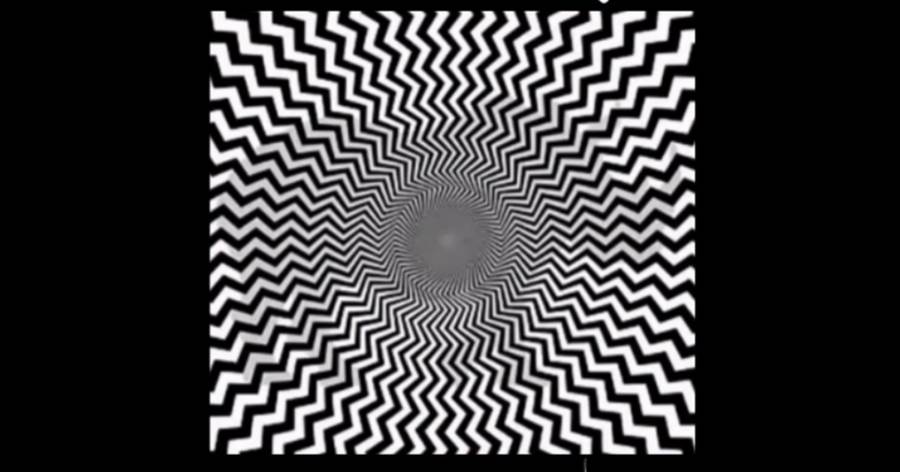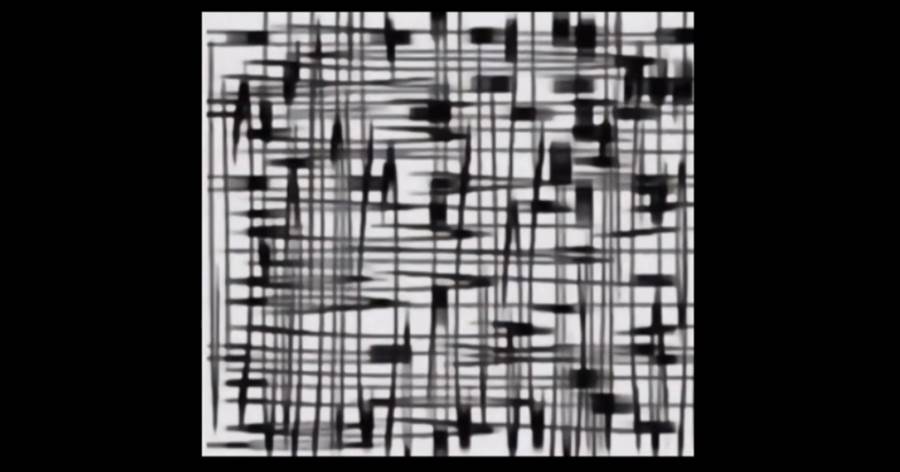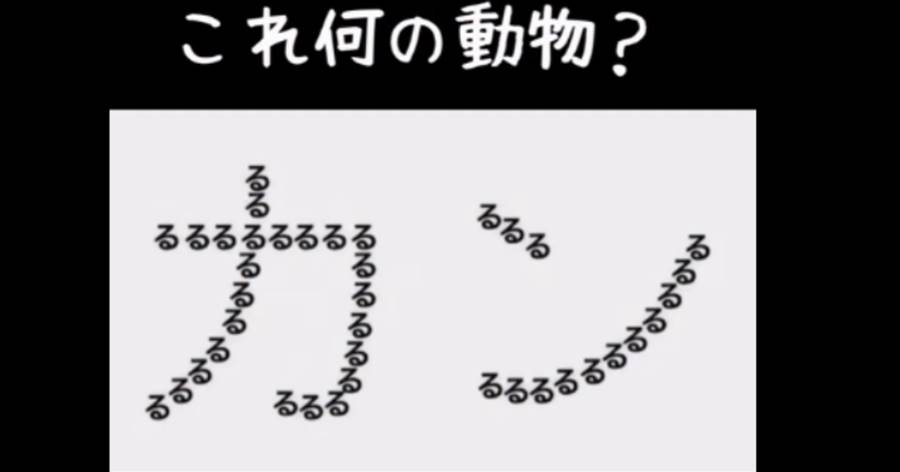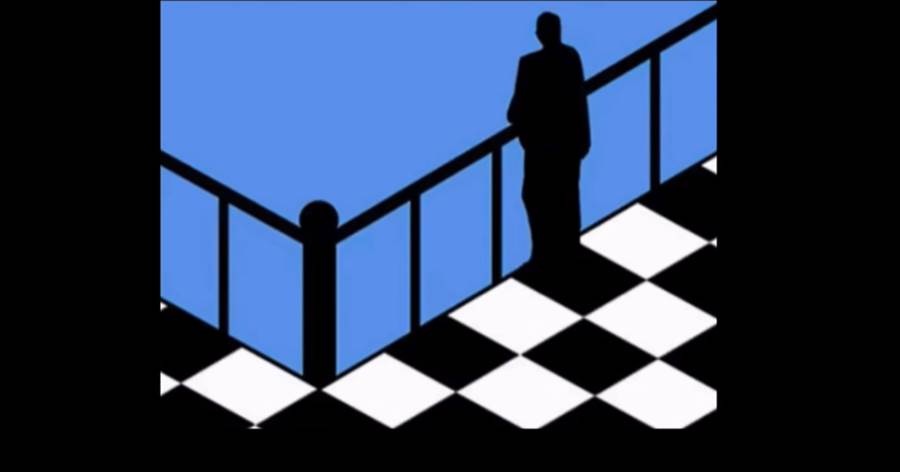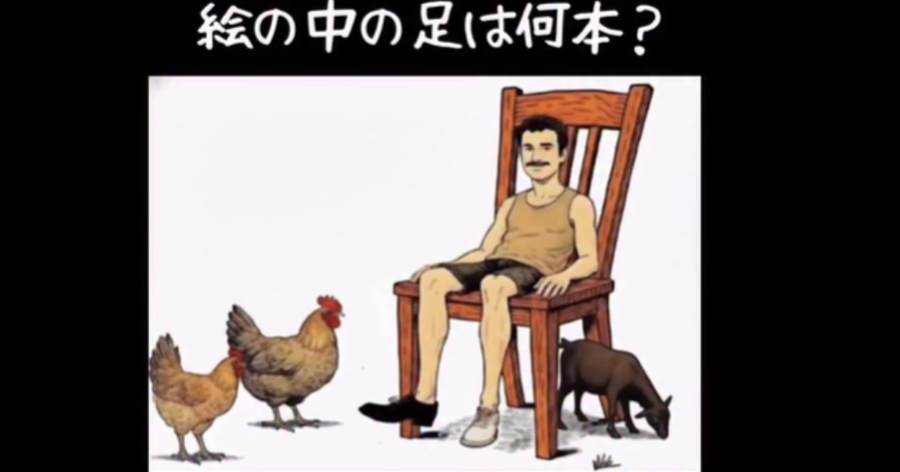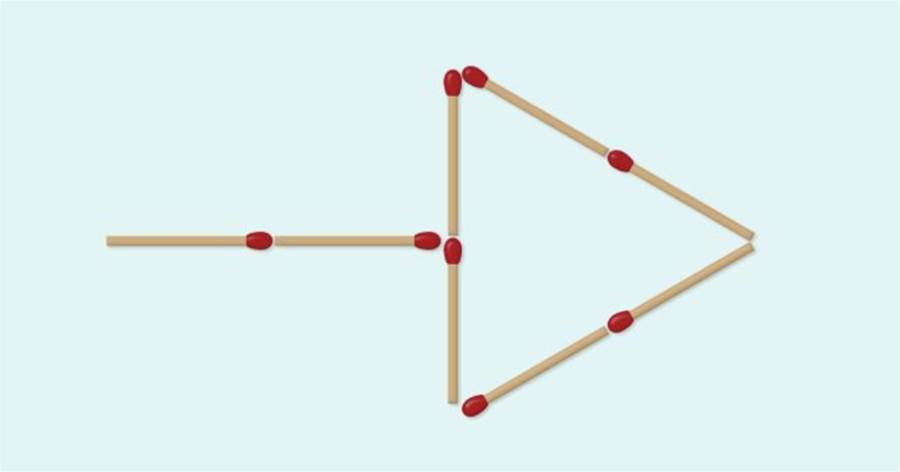
一見シンプルなこの火柴パズル。しかし、ここには隠された“再構築の美学”がある。
「ルールは簡単。火柴を4本だけ動かし、1つの大きな矢印を2つの小さな矢印に分けろ。」
目の前にあるのは、大きな矢印の形をした火柴の配置。左には長い棒、右には三角の先端。
あなたはこの形からどうやって「2つの矢印」を生み出す?
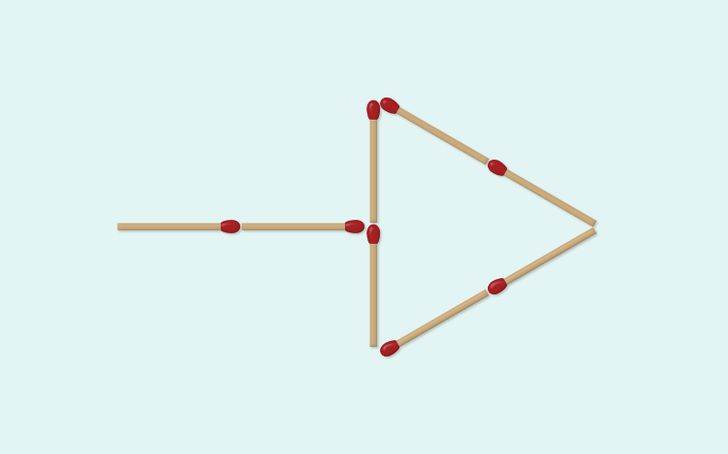
最初の形は、一方向を示す力強い矢印。火柴は全部で7本。
内訳はこうだ:
左に横たわる1本
中央に垂直な1本
右側の三角形を作る5本
ここから**「2つの小矢印」**を作るためには、ただ動かすだけじゃダメ。
火柴の位置と向きの概念をひっくり返す発想が求められている。
さあ、どう動かす?
まずは頭の中でシミュレーション。火柴の1本1本を分解し、どの部分が新しい矢印の“核”になり得るかを見極める。
大きな三角は2つに分割できそう?
左の横棒は2つに分ける“境界線”になれる?
無駄なく動かすにはどこを軸にする?
答えに近づくためのヒントは「上下に重ねる」という発想。左右に並べるよりも、縦の配置のほうが収まりが良い。
ついに発想の転換が起こった。
火柴4本を以下のように動かす:
左の横棒を半分に折るように動かし、上下に配置。
三角形の上辺・下辺をそれぞれ切り出し、新しい2つの三角形の上辺・下辺として配置。
元の垂直棒はそのまま“軸”として活用。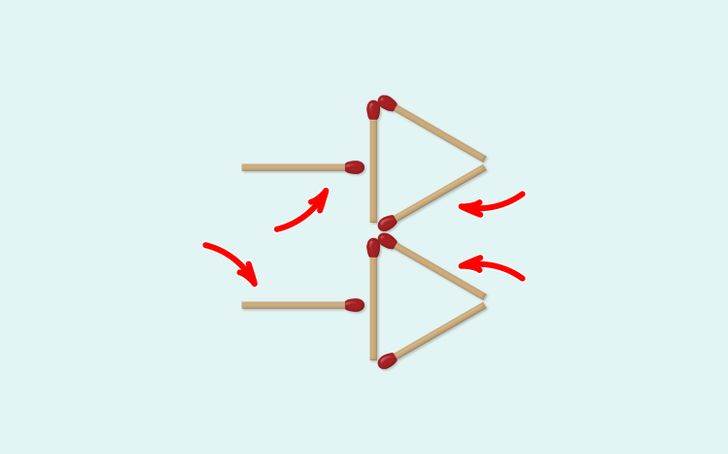
こうして2つの小さな矢印が、まるで兄弟のように上下に並ぶ。
大きな矢印の力強さが、2つの小さな矢印の“連携”に変わった瞬間だ。
少ない移動で最大の変化を生む——これこそ、このパズルの妙味だ。