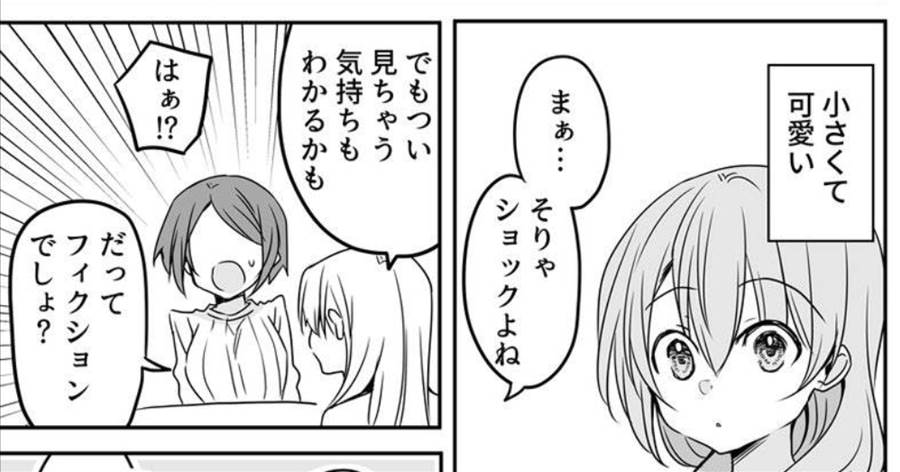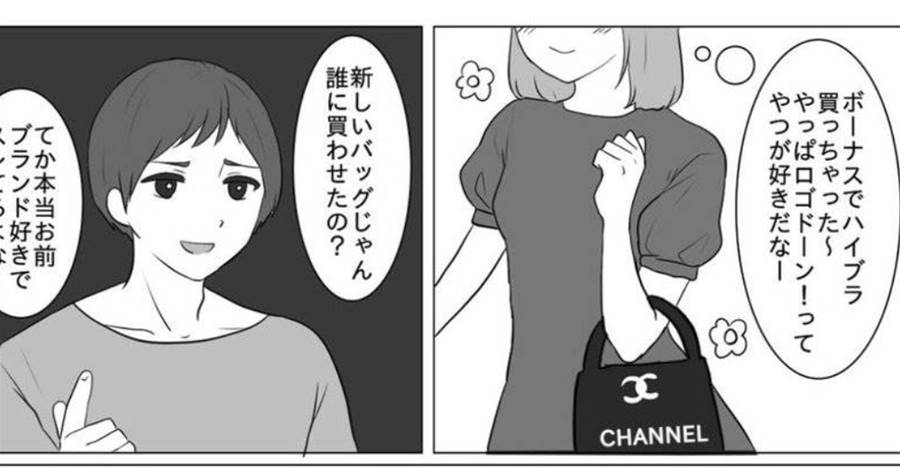開店前の静けさを破るのは、百合子――常連に「ゆりおばあちゃん」と呼ばれる妻の声だった。「今日も行くわよ、あなた。コーヒーは私が運ぶから、あなたは抽出に集中して」。気難しい店主の私に、彼女は四十年、変わらぬ調子で寄り添ってきた。
出会いは一杯の深煎りだった。香りに惚れた彼女が通い詰め、気づけば同じカウンターの内側に立っていた。
看板の「百合子カレー」も、試行錯誤の末に彼女が作り上げた――私はそう信じていた。
その日、若い客が二人、落ち着かない目で席を選んだ。百合子は笑顔のまま、私の横を通り過ぎる瞬間に囁く。「机の下で受け取って」。彼女の指先は、まるで日常の一部のように小さな包みへ触れた。
次の瞬間、店外から鋭い声が飛んだ。「警察です。麻薬取締法違反の容疑で任意同行を」。客の顔色が変わり、椅子が擦れる音が連鎖する。私は呆然と立ち尽くしたが、百合子は一歩も乱れない。署の者に向かい、淡々と告げた。「連絡ありがとうございます。長年の潜入、これで終わります」。
「潜入……?」問い返す私に、彼女は目を伏せずに言い切った。
「この店が取引に使われる情報がありました。私は店員として、そして“妻”として入りました。復縁も後悔もありません――任務でしたから」。四十年の結婚が、役割だったと。
私は詰め寄った。「なぜ、そこまで?」。彼女は静かに答える。「あなたは頑固で、アルバイトを一切雇わない。常連客として毎日通えば不自然で、張り込みはすぐ勘づかれる。
だから“夫婦”が一番自然だった」。さらに、私を落とすための微笑みさえ、事前のプロファイリング資料に基づいていたという。「あなたの知人に聞き込みもしました。好き嫌いも癖も、全部把握してから近づいたの」。
看板の百合子カレーについて尋ねると、彼女は少しだけ肩をすくめた。「あれは署で拘置者に出していた簡素なレシピ。具が少ないほど評判が良かったから」。
笑うべきか、泣くべきか分からなかった。
それでも、逮捕の瞬間に彼女が私を庇うように立った姿が脳裏から消えない。役割のはずの四十年で、彼女自身も何かを失い、何かを得たのではないか。私の手は震えたが、ポットから落ちる一滴は、確かに以前より澄んでいた。
看板はそのまま――カオスカフェ、今日も営業中だ。それでも、私は淹れる。今日も。
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=VWqDrRVQKGk,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]