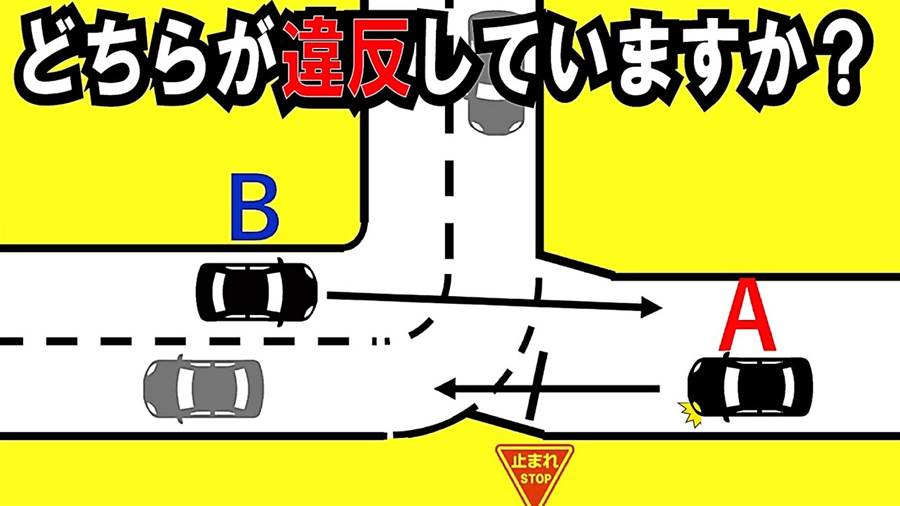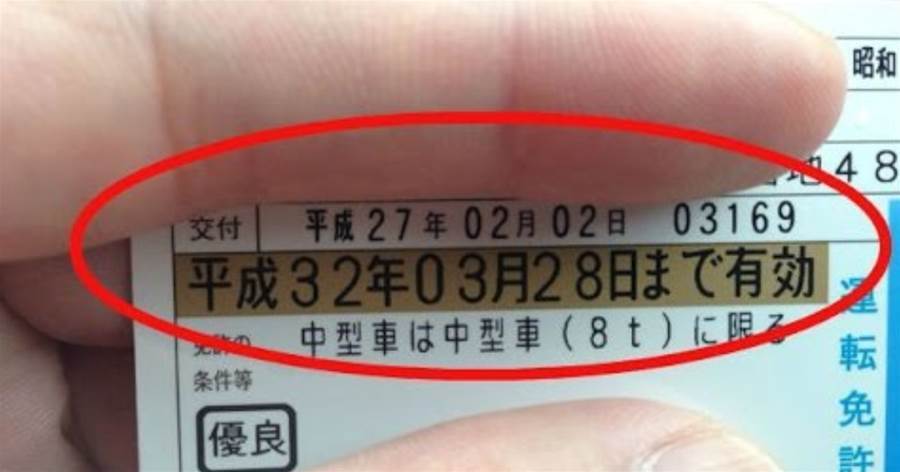車文化の移り変わりとともに、多くの言葉が時代の流れに飲まれ、姿を消していきました。昭和から平成初期にかけて使われた、車好きの間で生まれた言葉の数々。その多くは今ではほとんど耳にすることがなくなり、若い世代には理解されないものも。今回はそんな懐かしい車用語を10選にまとめ、背景や物語を紐解いていきます。もしこれらの言葉を今でも使っていたら、あなたは「車好きの昭和オジサン」かもしれません。
1. グローブボックス

グローブボックスとは、車の助手席前にある収納スペースのこと。元々はクランクハンドル操作時に手を守るための革手袋を収納する場所だったため、この名前が付けられました。時代が進むにつれて手袋は不要となり、収納スペースの目的も変わりましたが、名前だけはそのまま残ったのです。
2. 助手席のナビシート
「ナビシート」とは、カーナビが普及する前、助手席に座る人が地図を広げてドライバーを導く役割を指していました。
ラリー競技の影響を受けて生まれたこの言葉は、長距離ドライブには欠かせない存在でしたが、カーナビの普及でその役割は終焉を迎えました。
3. おもステ(重ステ)

「おもステ」は、パワーステアリングが普及する前の、操作が非常に重いハンドルを指す言葉です。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=Bo5sqBb9fmo,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]